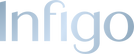日本人の青と緑⑯
今回から主に緑を見ていきます。
緑の普及による青の変化を見たいのですが、青と同様に緑も今の認識とはかなり違うため簡単ではありません。
◆奈良時代の緑
日本書紀に色名として出てくる「緑」は色制と虫の色の記述だけです。
日本人の青と緑⑭でも紹介しましたが、色制の記述では「緑」「深緑」「浅緑」が登場します。ただし、色味については平安時代に書かれたレシピの確認以外に知る術がなく、当初は全然違っていたという可能性もあります。
日本書紀における緑認識の唯一のヒントは皇極天皇紀にあります。
「この虫は、常に橘の樹または曼椒(ほそき)に生まれる。その長さは四寸ほどで太さは親指ぐらい。色は緑で黒い斑があって、姿は蚕に似ていた。」というものです。
この虫はアゲハ蝶の幼虫だと解釈されています。こちらは参考画像(小さくしてあります)です。
下の図はこの画像から抽出した色です。日本書紀の完成は720年ですので「奈良時代初期の緑」と考えて差し支えないと思います。
| 参考画像から抽出 | ||
| #aed264 | #a4d349 | #9fcb40 |
元々みどりは「瑞々しさ」「若々しさ」や「生命力」を表現するために使われていたようですので、こういう色を「緑」とするのは自然です。
万葉集では「緑児・緑子・みどりこ」といった言葉も出てきています。小さい子供のことです。奈良時代の戸籍では、三歳以下の男児を緑児(りょくじ)と記していたそうですから、とにかく「若い」がみどりだったと考えられるのです。
その後、平安時代に向けて段々と色彩語としての「緑」が定着していきます。それを機に青と緑がきちんと色相を分かち合えば良かったのですが、そう単純にことは運びません。
◆清少納言のみどり
まずは、枕草子(1001年頃完成)における緑の表現をいくつか紹介します。
枕草子は世界最古の随筆文学で、季節の移ろいや装束の色合いなどを写実的に捉えています。その鮮やかな表現からは著者である清少納言の優れた色彩感覚が伺えます。
A. たそばの木、しななき心地すれど、花の木どもちりはてて、おしなべてみどりになりたるなかに、時もわかず、こきもみぢのつやめきて、思ひもかけぬ青葉の中よりさし出でたる、めづらし。(40段)
「たそばの木は、品のない感じもするが、樹木の花が全部散ってしまって大体が緑になった中、秋でもないのに濃い紅葉の芽がつやつやと、思いもかけず青葉の中から出ているのは新鮮だ。」といった意味になります。
清少納言は「そばの木」に花が似ている「カナメモチ」を「たそばの木」と呼んでいたようです。
| カナメモチ |
カナメモチの若葉
|
 |
 |
垣根でよく見かけるこの植物のことです。確かに赤い芽が出てきます。
普通に「緑」が使われているようにも思いますが、「全体的にみどり」としつつカナメモチの古葉を「青葉」としている点が気になります。
「おしなべてみどりになりたるなかに」は木々が全体的に新緑・若葉になっていることの説明ですが、その「みどり」の中にこの青葉は含まれていないのですね。
B. 花なき頃、みどりなる池の水に紅に咲きたるも、いとをかし。(66段)
これは睡蓮の説明で、「花のない頃、緑色の池の水に紅く咲くのも非常に情趣にあふれている」という部分です。赤と緑の対比で描いていますから、この「みどり」は色名として使われているようです。
ただ、何が「みどり」なのでしょう?
他に花が無いような時期ということで、夏に植物プランクトンの色になっているということでしょうか。あるいは水草が覆っている感じかもしれません。
 |
 |
夏の瑞々しい植物が水面に映っているということも考えられます。その方が綺麗かもしれません。もしかすると水面の色は関係なく、周辺に「みどりの木々」があれば「みどりなる池」なのかもしれません。
 |
 |
C. 草葉も水もいと青く見えわたりたるに、(223段)
これは初夏の山里の様子を示した文に出てきます。
「五月の頃などに山里を牛車で移動するのは、大変趣がある。草葉も水もたいへん青く一面に見えている中で、表面は何の変化もなくて草木が生い茂っているところを、長々とまっすぐに行くと、草木の下にはなんともいえないほどきれいな水があって、深くはないのだけれど、人などが歩くときに水がはね上がるのは、趣がある。」という文です。
牛車で移動していたとすると、こんな場所でしょうか。

ここで「草葉はみどり、水あをく」としてくれたら色々とはっきりするのですが、残念ながら両方とも青です。
Bと似たような状況だと思いますが、緑と青の違いがあります。
若葉・新緑だけを緑としているのでしょうか。Aのカナメモチの古い葉を青葉と表現していますから、清少納言はこのような区別をしていた可能性が高いと思います。
|
あを
|
みどり
|
 |
 |
D. 日はいとうららかなれど、空は緑に霞みわたれるほどに、(260段)
この文では空を緑だとしています。現代語訳でも普通に「空は青く霞みわたり」となっていました。ただ、霞みわたっているのですから完全な青空ではなさそうです。
清少納言が仕えている中宮様(定子: 第66代一条天皇の皇后)登場の場面で、「日はとてもうららかだが、空が緑に霞みわたっているところに、女房の装束が美しく映えて、立派な織物やいろいろな色の唐衣などよりも、優雅でおもしろいこと、この上ない。」と語っています。
こういう感じでしょうか。
「青い空」よりも先に「緑の空」が生まれることになりましたが、「空が青い」は「漠」の雨が降り出しそうな曇ったニュアンスになってダメなのかもしれません。結局、文献の上では江戸時代になるまで「青い空」は出てこないそうです。
ひょっとすると、Bの「みどりなる池の水」というのは「みどりの空」が水面に映った状態なのかもしれません。絵画のような描写をしたことになりますが、稀代の才女ですから何があっても不思議ではありません。

「みどりの池」ではなく「みどりなる池」という言い方も、これだと納得です。
睡蓮と言えばモネですね。水面に空が映っている作品も多いです。
睡蓮の池、緑の反映 (制作年: 1920-1926)
「みどりなる池」とした意図はこういうことであった可能性もあります。映った空が植物と同化して浮いているようにも見えます。
◆和泉式部のみどり
和泉式部の「みどり」を紹介します。和泉式部は清少納言や紫式部と同じ時代に生きた女性歌人であり、当代最高峰の評価を受けた古典短歌界の頂点の一人です。
松はその もとの色だに あるものを すべて緑も 春は殊なり
「松はいつも緑ではあるが、春は格別だ」といった意味で、冬でも緑だということになりますから、少なくともこの緑は「新芽」のことではありません。語順や言い方が凝っていて判断は難しいですが、「松はすべてみどり」という文が成立しているようですので、基本的には色名と捉えて問題ないと思います。しかも、現代の緑認識に近づいている気がします。
|
兼六園の松(冬)
|
兼六園の松(春)
|
 |
 |
これに似ている歌を見つけました。源宗于(みなもとのむねゆき)という歌人の歌です。この人が亡くなったのは940年で、和泉式部が生まれたのが978年ですから、おそらく100年くらい時代が違います。
ときはなる 松のみどりも 春くれば 今ひとしほの 色まさりけり
常盤(ときわ)は常緑樹のことですから、歌の内容はほとんど同じです。微妙なところですが、このみどりは松葉全体を指していると思います。「松のみどり」と「松はみどり」の違いですが、和泉式部までの100年間で「みどり」は叙述用法が可能な色彩語に進化したと言えるのではないでしょうか。
もう一首、和泉式部の歌を紹介しておきます。
とぶかとて みどりの紙に ひまもなく かき連ねたる 雁がねを聞く
「緑の紙にびっしりと書いたように雁が飛んでいて、その音がする」と言っています。
この背景が空であることは間違いありません。「空がみどり」であることが当たり前でないと成立しない比喩で、間接的な「みどりの空」です。
そうなると「みどりの空」はかなり広く使われていたのかもしれません。他にも同時期の歌に「みどりの紙」の用例がありましたので、宮中では流行っていたのだと思います。
これより前にこんな歌も詠まれていました。
久方の みどりの空の くもまより こゑも仄かに かへるかりがね
大納言師氏 (913-970)
これが「みどりの空」の最初だそうです。
「秋の空の緑の隙間から、かすかに聞こえる雁の声が故郷へ帰っていく」といった意味です。
この他にも雁と緑の空がセットで出てくる歌があるのですが、雰囲気からして青空ではありません。雁は秋の訪れを告げる鳥のため、その鳴き声に自身の悲しみや寂しさを重ねるというのが常套手段だったようです。
このみどりに関しては、もう古代の「あを」と同じ感覚だと思います。平安文学においてはどんな色の空であっても「みどり」で問題ないのかもしれません。
◆漢詩の影響
「みどりの空」に関しては漢詩・漢語の影響が相当にあったようで、「碧」の解釈の問題によるところが大きいと思います。
前回記事で「青碧(せいへき)」を紹介しましたが、今なお「碧」の読みは「あお」でも「みどり」でもあり、非常に難しい漢字だと言えます。ただ、「碧」は2022年赤ちゃんの名前ランキングにおいて男の子の1位だったそうです。読み方は「あお」や「あおい」です。
そもそも中国語の青と緑が極めて難解なのですが、元々「碧」は濃い青で英語だと"azure" です。"blue" から"green" まで「青」とみなしている日本に「青碧」という青緑色がやって来たのですから、さすがに混乱しそうですね。「みどり」が存在していればそれを「碧」の読みに当ててもおかしくありません。
また、漢詩では碧天(へきてん)、碧落(へきらく)、碧空(へきくう)のように、空に関するフレーズで「碧」が多用されています。全て青天の表現なのですが、これを引用すれば当然「空の色は碧」となるでしょう。こんな感じで「みどりの空」が生まれたのだと思います。
藤原氏の時代、漢詩をそらんじることは一種のステータスであり、「碧」が出現する漢詩になぞらえて空の色を示すことは知的かつ最先端で、承認欲求を満たすのに丁度良かったのだと思います。文献からはわからないですが、天気に関係なく、こぞって「みどりの空」を使っていたのかもしれません。宝石の名称に使われている字なのですから、美しい表現だとされていたはずです。
◆まとめ
元来、「漠」が青の始まりであり、最初は空の色を表現したものでした。にも関わらず、江戸時代の文献まで「青い空」は出現しません。何とも不思議なことです。
奈良時代まで晴れた空をどう表現していたのか全くわかりませんが、誤解もあって「みどりの空」という新しい空の表現を得ることになりました。雲一つない紺碧の空を「みどり」と形容していたかはわかりませんが、「基本的に空はみどり」のような暗黙のルールができたようです。
やはり、今のみどりとは解釈が違うため、すべての検証が難しいです。青と碧の取り違えがあったにせよ、空の色をみどりとしてしまう根底には、初めから相当な感覚の違いがあったと考えられます。
ひとまずは明度の問題なのでしょうか。奈良時代や清少納言の感覚だと、明度が低い場合は「みどり」ではないのかもしれません。

例えばこのチャートだと緑は上の2~3段だけで、それ以外は青だったのかもしれません。最上段の一番左は「緑に霞みわたれる空」の感じで、右の方はアゲハ蝶の幼虫の色です。
こういう色相だけでなく、blueからgreenであれば、高明度は全て緑となり、それ以外は基本的に青だったということもあり得ます。元々が「青」は色調の表現で「緑」は状況や状態を説明するための言葉ですから、一つの条件で明確に分ける行為は不自然なのですが、そうなる傾向があったという可能性は高いと思います。
この仮説を極端な2例で示しますと、こうなります。
| 1: 青 | 2: 緑 |
| #298e30 | #a4d1e1 |
植物プランクトンが1で、空は2。
空が常にみどりなのであれば、「みどりなる池」には本当に空が映っていたのかもしれません。本当にこの仮説のように使い分けているとすれば、清少納言の色彩感覚は相当なものです。
一方の和泉式部は「松葉は常に緑」で「夕方の空がみどり」と考えていたようですので、歌としては秀逸かもしれませんが「みどりの色彩観」という一点で比べてしまうと物足りない感じがします。
次回は源氏物語のみどりを紹介します。
ここでもみどりの空が出てきますので、お楽しみに。
| 当記事には筆者の推察が数多く含まれています。また、あくまでもInfigo onlineに興味を持っていただくことを目的としておりますので、参考文献についての記載はいたしません。ご了承ください。 |