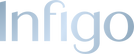日本人の青と緑⑮
前回までに奈良時代の前の辺りまで色名を追ってきましたが、基本的に青は色名というよりも色グループ名でした。明・暗・顕・漠の考え方が続いているようでもありますし、中国の青が緑色だったことで幅の広さが決定的になったとも言えます。
今回は万葉集を中心に飛鳥時代から奈良時代までの色彩感覚を考察します。
◆奈良時代の文献の青
この時代の青には以下のようなものがあります。
[青色~緑色]
青淵、青頭鶏、緑青、金青、青碧、青き盖、青角髪、青柳、青根我峯、青旗、青丹吉
[不明]
青雲、青春、青馬/青駒
説明は省略しますが「青き盖、青角髪、青柳、青根我峯、青旗」は全て植物系、「青丹吉」はすでに紹介済みの「あをによし」ですので、これら以外の「青」を見ていきます。
青淵
青淵というのはこのような淵のことで、これが万葉集に出てきます。
もっと深い淵を想定していたかもしれません。
虎に乗り 古屋を越えて青渕に 鮫竜(みづち)捕り来む 剣大刀(つるぎたち)もが
これは「虎に乗って家を飛び越え、青く深い淵にいる鮫竜を捕らえられるような刀がほしいよ」といった意味の歌になります。
鮫龍は蛇のような姿をした想像上の動物で、日本書紀の仁徳天皇紀にも「淵に住む鮫龍が毒を吐いて人々を苦しめた」とあります。こういった淵は大昔から恐ろしいという印象があったようです。
五行説以降「青」には春のイメージが追加されましたが、元々は「漠」から続く不明瞭な感じを表す言葉です。画像の淵は鮮やかな青ですが、この青淵は前回記事の青霧と類似した使い方なのかもしれません。純粋な色表現ではない「不穏」の青です。
単なる「淵」ではなく「青」を足すことで、どこまでも深く何かが出てきそうな感じを演出できたのだと思います。
青頭鶏
これは「青い頭の鳥」なので鴨のことです。
この3文字でカモと読ませるような言葉遊びが万葉集には多く見られます。戯書(ぎしょ)あるいは戯訓(ぎくん)と呼ばれるそうです。

こちらの青も普通ですかね。色彩語としての緑がこの時点で定着していないこともわかります。
カワセミもそうでしたが(鴗鳥の青き御衣)、構造色の青系は素直に青を使っています。おそらく色彩が複雑であることも青としやすい要素なのでしょう。
こういう光沢も青だったそうです。
緑青・金青・青碧
続日本紀の緑青(ろくしょう)と金青(こんじょう)、僧尼令(そうにりょう)の青碧(せいへき)は初登場の色名です。それぞれ現在ではこのような色が示されています。
| 緑青 | 金青 | 青碧 |
| #5BAD92 | #003775 | #478384 |
緑青はマラカイトの色のことです。つまり、「あをによし」の青丹と同義だと思われます。
金青(こんじょう)の「こん」は「紺」と同じです。つまり、紺青ということになります。この色は岩群青(アズライト: 藍銅鉱)を顔料とします。日本人の青と緑⑬でも紹介しましたが、西壁女子群像のセンターの女性の袴の色で使われています。
青碧は中国の宝石の名称で青緑色をしているそうです。僧侶の服装の色として出現します。中国では「青 ≒ "green" , 碧 ≒ "blue" 」なので青碧は青緑色を表すのですが、現在「碧」の訓読みは「あお」と「みどり」の2種類です。
当時の公式見解としては「青」と「碧」が同類だとみなされています。とは言え日本では"blue" も"green" も「青」ですし、「緑」もまだ生まれて間もないはずですから、「碧」の解釈はかなり難しかったはずです。青碧の色が青緑色なのですから、「青」を"blue"だと考えてしまうと、「碧」は"green" だと勘違いするでしょう。そうなると真逆です。
次回記事では「碧」の難しさが影響したと思われる例を紹介します。
青雲
再度青雲が出てきました。(前回の青雲はこちら)
今回は万葉集の持統天皇の歌です。
向南山(きたやま)に たなびく雲の青雲の 星離れ行き 月を離れて
「北山にたなびいている青雲が、星からも月からも離れて遠くに行ってしまった」という歌ですが、夜の雲を青雲と呼んでいます。雲によって明暗が生まれているのでしょうか。

こういう感じで雲が離れていったのでしょうか。
「漠」のイメージに近いですが、こうした「青」は色とは無関係なのかもしれません。侘しさ、無常観といった特別な感情を「青」に託しているような気がします。
青春
751年に作られた懐風藻(かいふうそう)という日本の漢詩集に「青春」が出てきます。
「縦賞青春日、相期白髪年」
これは刀利宣令(とりのせんりょう)という官人の詩の一節で、「若い頃の日々を楽しみ、白髪になるまで共に人生を歩む」といった意味になるそうです。現在の青春と同じ意味で使われていますね。
「青春の日」ですから直接的には全く色彩が関係しない「青」ですが、五行説の「木」には「春、青」に加え、「新緑」や「若さ」という要素も対応しています。
中国では少なくとも3~4世紀までに「若い頃」を意味する「青春」が使われるようになっていますが、飛鳥時代か奈良時代の人が五行説と共に取り入れていたことになります。
青馬・青駒
万葉集に登場する「青馬」「青駒」を紹介します。日本人にとっての「青」の複雑さを象徴する例です。その名の通りだとどちらも青い毛並みの馬ということになりますが、どういうことでしょう?
まずは宮廷の新春行事である「青馬の節会」に関する歌に青馬が出てきます。「青馬の節会」は天武天皇10年(681年)の1/7に行われたのが最初だそうです。
この恒例行事に際し、歌人でもある官人の大伴家持(おおとものやかもち)が以下の歌を用意していました。
水鳥の 鴨羽の色の 青馬を 今日見る人は 限りなしといふ
「今日、鴨の羽の色をした青馬を見れば、無限の寿を得るそうですよ!」というような意味です。大伴家持はこのイベントに携わっていたようで、キャッチコピーのような効果を期待したのだと思います。

「鴨の羽色」というのはこの頭のことだとしている説明が多いのですが、そんな馬がいるでしょうか。頭の部分を「羽」とするのも少し不自然に感じます。私は翼の辺りを指しているような気がします。特に裏側は最も「青」と呼ぶにふさわしい感覚だと思います。
一方、青駒が出てくる歌には色の記述がありません。
青駒の 足掻(あがき)を早み 雲居にそ 妹(いも)があたりを 過ぎて来にける
「馬の歩くのが早いので、妻のいるところは見えなくなった」という柿本人麻呂の歌です。こちらの青駒については芦毛の馬だと解釈されています。確かにこの頃の「アヲい馬」で真っ先に芦毛を想像するのは自然です。

オグリキャップ(芦毛) 1993年
とは言え、青馬と青駒が別の色だとも考えづらいのですが、どうなのでしょう?
馬の毛色の呼び方に関しては現代でも不思議で、
青毛:全身真っ黒
青鹿毛(あおかげ):ほとんど黒で、局所的にわずかに褐色
という2種類の青があります。
この2種類は基本的に黒いです。馬の世界だと「真っ黒」が「青」になります。真っ黒だと光の加減でほんの少し青みを帯びて見えることがあるようなのです。鴨の頭のような光沢が出ているとすれば「青馬の節会」はさらに難しくなります。
 |
 |
| シーザリオ(青毛) | キズナ(青鹿毛) |
「青馬の節会」という行事ですが、たくさんの馬を庭に出し、眺めて宴会をするという催しで、「その馬を見れば病気にならない」という願掛けの意味を持ちます。この行事は現在も続いているのですが、平安時代中期以降は「白馬節会」と書かれるようになります。しかも、「あおうまのせちえ」という読みはそのままであったというのが定説です。
京都の上賀茂神社で白馬奏覧神事(はくばそうらんじんじ)、大阪の住吉大社で白馬神事(あおうましんじ)、鹿島神宮では白馬祭(おうめさい)という名で、今でも当時と同じ1/7に催されています。今は完全な白馬です。
上賀茂神社の白馬
当初は中国故事に従って黒毛の馬を使用し、その後平安中期に白の方が神聖だということで、「あおうまのせちえ」という読みをそのままに、表記を「白馬節会」とし、芦毛や灰色の馬に変えたという説が有力だそうです。とは言え、最初から芦毛の馬であったという説など複数の考え方があり、決着はついていません。
どうやら、古代中国の青馬というのは本当に黒い毛並みだったようなので、きちんとそれに倣ったのかどうかが争点になると思います。中国の青も本当に難しいですね。
「最初から芦毛」を推す方々の大部分は、
・大伴家持は「青」という呼称から鴨の羽の色を連想しただけ
・まだ見ていない時点での歌なので参考にならない
という意見を持っているようです。
私は「最初から芦毛の馬で、鴨の翼の羽の色に喩えた」を推したいと思います。芦毛の馬は加齢によってどんどん白くなりますので、表記を「白馬」に変えるのも自然です。
|
1990年のオグリキャップ
|
2008年のオグリキャップ
|
 |
 |
例えば、アオサギはこのような姿をしています。
アオサギ
風土記にも「青鷺」と出てきます。 こういう感じが最も自然な「昔ながらの青」だったのだと思います。これが青なのですから、若い頃のオグリキャップは青馬です。
鴨の羽色にも似ていますし、最初の青馬の節会にいたのは芦毛の馬だったのではないでしょうか。
◆まとめ
今回は万葉集時代の青をたくさん紹介しました。若さを意味する青が初めて出てきましたが、それ以外は大きな変化がありません。不思議なアヲが残っているということも含めて、それほど状況は変わっていません。
また、公式の文書に単なる「青」は出てきません。七色十三階冠の冠素材であった「青絹」を最後に、単体の「青」はないのです。ここまで徹底されていると、誤解を避けたというよりも、何か「青」が次元の異なる言葉であったという気がしてきます。
結局、「青という色」のような考え方はなかったのかもしれません。色グループと言っても色相では全く説明できない部分がありますし、かと言って青の複雑さは色調だけの問題でもありません。"blue" や"green" に関しては彩度に関係なく青でいいのかもしれませんが、その他の色相でも彩度が低く明度が中程度であれば青となり得ます。
さらには、「見えづらい」「曖昧」「微妙な色が隠れていて複雑」という状況を補足するような「青」や「物寂しい」「深淵」「怖い」というような感情を込めた「青」もあります。象徴的な青い物がある訳でもなく、色以外の要素が色の表現に影響するというのは非常に日本的だと言えるのかもしれません。
奈良時代までの時点で青が使われた条件を整理してみます。
①植物の色
②構造色のような複雑な青系の色彩
③色温度が高く、彩度が低い状態
④灰色系
⑤曖昧、よく見えない、視界が悪い状態
⑥不穏な状態、不安な状況
⑦若いこと
こういった感じでしょうか。
青が色彩に関する言葉であることは否定できませんが、ここまで複雑だと色名とするには少し無理があるのかもしれません。
次回からは平安時代になります。
ようやく緑がたくさん出てくるようになりますし、文献も豊富になります。
お楽しみに。
| 当記事には筆者の推察が数多く含まれています。また、あくまでもInfigo onlineに興味を持っていただくことを目的としておりますので、参考文献についての記載はいたしません。ご了承ください。 |