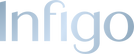賀茂伝説
風土記は713年に元明天皇が諸国に命じ、各国それぞれで編纂されました。
各地方の文化風土などが記載された報告書のようなものなのですが、山城国の風土記は現存しておらず、他の書物に引用される形で内容が伝えられています。
その中に初代皇后誕生のお話によく似た説話があります。
| 古代京都を拓いた賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)の娘である玉依媛命(たまよりひめのみこと)は、鴨川の上流から流れてくる丹塗矢を拾って持ち帰りました。矢を寝床の辺りに置いていたところ、玉依媛命は懐妊し、賀茂別雷命(かもわけいかづちのみこと)が産まれました。その後、成人した賀茂別雷命に祖父の賀茂建角身命が「父に酒を飲ませよ」と命じると、賀茂別雷命は屋根に穴を開けて天に昇りました。丹塗矢、すなわち父神は、火雷神(ほのいかづちのかみ)だったのです。 |
賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)と玉依媛命は賀茂御祖神社(通称: 下鴨神社)のご祭神、賀茂別雷大神が賀茂別雷神社(通称: 上賀茂神社)のご祭神です。
また、火雷神は向日(むこう)神社に祀られています。
古くから縁結びと子育ての神さまとして信仰されてきた下鴨神社では、このお話を元にした「干支丹塗矢」をいただくことができます。
干支丹塗矢
(画像元: 下鴨神社HP)
上賀茂神社でも「立て丹塗矢」という御神矢をいただけるようです。
立て丹塗矢
(画像元: 上賀茂神社HP)
また、八咫烏は賀茂建角身命の化身だとされていて、山城風土記にも神武天皇を先導してから下鴨地区に鎮座するまでのルートが記されています。
さらに、日本書紀に登場する金鵄(きんし:金のトビ)も賀茂建角身命の化身とされています。
神武天皇と金鵄
(月岡芳年「大日本名将鑑」より/ PD)
この絵の鳥は八咫烏ではなく金鵄で、ナガスネヒコ軍との戦いで活躍しています。
敵は金鵄が放つ光に目がくらんでいるようです。
なお、神武天皇の母神は玉依姫(たまよりひめ)と言いますが、玉依媛命(たまよりひめのみこと)とは無関係です。時代も近いので非常にややこしいですね。
また、ニニギの母神も玉依姫命の別名を持っているそうです。
「玉依姫」は「御霊の依り代となる姫=巫女」という意味を持つため、この名を持つ神が複数存在する事態になったようです。
| 当記事には筆者の推察が数多く含まれています。また、あくまでもInfigo onlineに興味を持っていただくことを目的としておりますので、参考文献についての記載はいたしません。ご了承ください。 |