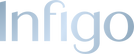古墳築造の時代背景
古墳築造の時期についてまとめました。
| 西暦/時期 | 内容 | 帝位(代数) 日本書紀参考 |
帝位(代数) 古事記等参考 |
| 57 | 後漢の光武帝より倭奴国王が金印を受け取る | ||
| 2世紀頃 | 纒向において巨大集落の建設が始まり、やがて古墳が築造されるようになる | 景行天皇(12) 成務天皇(13) |
開化天皇(9) 崇神天皇(10) |
| 238 or 239 | 卑弥呼が魏に使いを送り「親魏倭王」の号を受け取る | 摂政:神功皇后 | 崇神天皇(10) |
| 3世紀中頃 | 箸墓古墳築造 | 摂政:神功皇后 | 崇神天皇(10) 垂仁天皇(11) |
| 391 - 404 | 倭・高句麗戦争 | 仁徳天皇(16) 履中天皇(17) |
応神天皇(15) 仁徳天皇(16) |
| 5世紀前半 | 大仙陵古墳築造(伝 仁徳天皇陵) | 履中天皇(17), 反正天皇(18), 允恭天皇(19) | |
| 527 | 磐井の乱 | 継体天皇(26) | |
| 538 | 百済より仏教伝来 | 宣化天皇(28) | |
| 6世紀中頃 | 王塚古墳築造 | 欽明天皇(29) | |
| 593 | 聖徳太子摂政となる | 推古天皇(33) | |
| 645 | 乙巳の変 | 皇極天皇(35) | ― |
| 663 | 白村江の戦 | 中大兄皇子=天智天皇(38) | |
| 672 | 壬申の乱 | 弘文天皇(39) 天武天皇(40) |
|
| 694 | 藤原京に遷都 | 持統天皇(41) | |
| 藤原京時代 | 高松塚古墳築造 | 持統天皇(41) or 文武天皇(42) | |
| 710 | 平城京遷都 | 元明天皇(43) | |
古墳時代の初期に最初の巨大古墳である箸墓古墳が三輪山の山麓(纏向)に築造されました。奈良県桜井市には数多くの古墳が存在し、箸墓古墳はそのアイコンとなっています。
その後、難波高津宮に都が移されたことで古墳築造エリアは河内に移動します。日本最大の古墳である仁徳天皇陵は非常に有名で、世界遺産百舌鳥・古市古墳群の代表です。
| 箸墓古墳 | 大仙陵古墳 |
 |
 |
私は仁徳天皇陵と教わりましたが、大山古墳・大仙古墳・大仙陵古墳のように可能な表記がたくさんあります。様々な理由で教科書表記も色々と変遷があるようです。
その後の王塚古墳築造から高松塚古墳築造までの期間に様々なことが起こっていますね。飛鳥時代がすっぽりと入っています。高松塚古墳は古墳時代の終末期に築造されました。
なお、箸墓古墳の築造時期と被葬者については様々な議論がなされています。
宮内庁はこの被葬者を倭迹迹日百襲姫命(やまとととひももそひめのみこと)と治定しています。百襲姫は第7代孝霊天皇(在位: 紀元前290-215年)の皇女で、崇神天皇に神意を伝える役目を担っていました。巫女的な性格を持つ女性で、日本書紀では大物主神の妻になったとされています。ただ、崇神天皇陵より巨大なのはやや不自然です。
箸墓古墳の被葬者が卑弥呼だとする研究者もいます。この説は大正時代から存在していて、卑弥呼=百襲姫とされているようです。つまり、邪馬台国=ヤマト王権ということになります。卑弥呼が亡くなったとされるのは248年となっていますので、こうした説があるのも頷けます。
ただ、魏志倭人伝自体も信憑性が疑問視されていますし、箸墓古墳は発掘調査ができないこともあって、決め手に乏しくはっきりしていません。そんな中、近年物質を透過する素粒子による調査が始まったことで箸墓古墳が改めて注目されています。
→古墳と宇宙の意外な関係?(なら歴史芸術文化村)
| 当記事には筆者の推察が数多く含まれています。また、あくまでもInfigo onlineに興味を持っていただくことを目的としておりますので、参考文献についての記載はいたしません。ご了承ください。 |