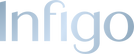日本人の青と緑⑪
アカとチヌでかなりの寄り道になってしまいましたが、アヲに戻ってきました。
古事記までは植物の色がアヲのメインで
アヲ=緑寄りの(青~緑)+灰がかった色
という感じでしたが、今回から古墳時代以降の色認識に目を向け、アヲの変化を探ります。
◆百済から漢字の色名が伝来
日本書紀によると、継体天皇(在位: 507~531)から欽明天皇(在位: 539~571)の時世に中国古典を教授するための博士が百済から何人も来日しています。これにより儒学が入ってきたのですが、それと共に陰陽五行思想(いんようごぎょうしそう)・陰陽五行説が伝わったと考えられています。
陰陽五行思想は、古代中国の戦国時代(紀元前5世紀~紀元前221年)に別々に生まれた陰陽思想と五行思想が、漢の時代(紀元前206年~後220年)になって合体したものです。
良く知られている陰陽道(おんみょうどう)は陰陽思想を起源として日本で独自に確立された呪術や占術の技術体系になります。
色に強く関係するのは五行思想の方で、万物は火, 水, 木, 金, 土の5種類の元素からなるという考え方です。五行説とも呼ばれます。
この5種類の元素はそれぞれ季節や色などに対応しています。
木=春=青
火=夏=赤
土=土用*=黄
金=秋=白
水=冬=黒
*土用: 立夏・立秋・立冬・立春の直前18日間
これらの青, 赤, 黄, 白, 黒は五色(ごしき)と呼ばれ、五色の短冊や鯉のぼりの吹き流しなど、日本では多くの場面で遭遇する配色です。
お寺の五色幕などのように青が緑、黒が紫になっていることもあります。

陰陽五行説の説明にはこうした図がよく用いられています。
相生(そうせい)というのは相手を生み出す陽の関係で、相剋(そうこく)は相手を打ち消す陰の関係だそうです。
日本においてこの陰陽五行説がどういう順で広まったかはわかりませんが、色認識の把握と漢字の獲得は同時だったと思います。
でも教わった直後から色を正確に把握することができたのでしょうか。
ひとまず「こういった色は青」というような説明は受けていたはずで、その上で「アヲ=青」と判断することになった訳ですから、少なくとも百済人の言う「青」と従来の「アヲ」はかなりの部分で一致していたと思います。
「漠」由来のアヲがどうなったかも気になりますが、古墳時代のことですから、このときの認識のズレを直接検証する方法はありません。その後の用例などから想像することになります。
◆冠位十二階
飛鳥時代になると色認識はさらに発展したはずですが、「飛鳥時代, 色」と言えば冠位十二階(603年)が思い出されます。
冠位十二階に関する記述は日本書紀と隋書倭国伝の2種類あるのですが、服と冠が同じ色だと書かれてはいるものの、残念ながら色名は出てきません。
ただし、五行説の5色に紫を加えた「6色」×「濃淡の2種」=12色 という江戸時代から続く有力説が存在し、下図のような感じの説明が多くみられます。
| 大徳 | 濃紫 |
| 小徳 | 薄紫 |
| 大仁 | 濃青 |
| 小仁 | 薄青 |
| 大礼 | 濃赤 |
| 小礼 | 薄赤 |
| 大信 | 濃黄 |
| 小信 | 薄黄 |
| 大義 | 濃白 |
| 小義 | 薄白 |
| 大智 | 濃黒 |
| 小智 | 薄黒 |
冠位の名称は「大小」×「徳・仁・礼・信・義・智」の12種であることは日本書紀に書かれていて、「徳」を除いた「仁・礼・信・義・智」は五常と呼ばれる儒教における道徳の5要素です。
五行説では万物が火・水・木・金・土に対応している訳ですから色々な5個セットがあります。
「相生の順」に並んでいるため、上下の順序は変えられないと思います。
| 五行 | 五時 | 五方 | 五常 | 五色 |
| 木 | 春 | 東 | 仁 | 青 |
| 火 | 夏 | 南 | 礼 | 赤 |
| 土 | 土用 | 中央 | 信 | 黄 |
| 金 | 秋 | 西 | 義 | 白 |
| 水 | 冬 | 北 | 智 | 黒 |
五常と五色の列を見てわかる通り、冠位十二階の有力説はこの部分に「徳-紫」を加えただけです。確かに合っている気がしますね。
ただ「薄白」というのは無理がありますし、白_薄グレー_濃グレー_黒の順で並んでいないと直感的な判断は難しいはずです。色落ちするリスクを考えても、濃淡の利用は厳しそうなのでこの通りではなかったと思います。
また、「青」は「春と木」に対応しているのですから、緑の方が自然だと思うのですが、実際はどうだったのでしょう?
青と緑の問題は常に付きまといます。
◆中国の青と日本の青
古代中国においては青と緑の色を区別する明確な概念が確立されていなかったと考えられ、古代の日本と同じ様にその辺りは全部「青」だったようです。
おそらく現代であれば五行説の「木」は「緑」にすると思いますが、この思想を確立した時代に「青」しか使っていなかったのであれば仕方ありません。
やはり、五行説で言う「青」は緑色なのです。すでに「緑」を把握していた可能性も高いですが、当時の百済の博士たちは、まずは森とか葉っぱなどを指差しつつ「青」の字を書いて「五色の青」を説明したはずです。
それを受けて、ひとまず「青」の解釈や読みを「アヲ」にしたのは当然だと思います。日本でも「青~緑」だったのですから。
ただ、その後「緑」という字もやってきてしまいます。どの時点でやってきたかはわかりませんが、もし「アヲ=青」だと定義した直後であれば相当に混乱するでしょう。
ここで、この時点での推論を英語の色名も使って整理してみました。
五行説伝来からの現在までの認識の推移を想像しています。
| Greenからblueまでをアヲと呼んでいたところにGreenが「青」だと教わったが、「青」の読みをアヲとした。 |
| アヲ | |||||||
| Green | Blue Green | Blue | Indigo | ||||
| 青 | 藍 | ||||||
| 五行説の青 | 青空の色 | ||||||
| Green | Blue Green | Blue | Indigo | ||||
中国では藍も古くから色として確立されていましたので、当時はこのような感じだったと思われます。晴れた空の色には「青」が使われています。ただし、「ほぼ黒」を「青」とする例が古典に多く見られるそうなので、表の一番右の色は「青」だったかもしれません。
百済の博士がどのように説明したかはわかりませんが、結果的には下図のように従来のアヲに青の字を当てただけになりました。
このことによって日本古来のアヲは守られることになります。
| 青(古来のアヲ) | |||||||
| Green | Blue Green | Blue | Indigo | ||||
| ひとまず、Green + Blue 全体が青となったが、その後「緑」という狭い範囲の漢字を獲得したことで、緑の範囲を除いた部分を「新しい青」として再定義した。 |
| 古来のアヲ | |||||||
| 緑 | 再定義の青 | ||||||
| Green | Blue Green | Blue | Indigo | ||||
時期についてはわかりませんが、最終的にはこのような感じに青と緑が分類されたはずです。しかしながら、大昔から全部の領域を「アヲ」と呼んでいたのですから、「緑」の出現だけですぐにその習慣をなくすことはできなかったと思います。
そもそも漢字を読める人はどれ位いたのでしょう。どのように定義されようがその情報にアクセスできない以上、全く関係のないことです。
そのため古来のアヲは色認識の伝来とは全然関係なく、ずっと後まで残っていたはずです。「アヲ野菜」などはその名残りなのです。庶民の間では「漠のアヲ」も残っていたかもしれません。朝廷・豪族・貴族が再定義の「青」を使っていたとしても、染物屋でもやっていない限り影響はなかったと思います。
両者の現在の認識はこのような感じだと思います。
| 緑 | 青 | 藍/紺 | |||||
| Green | Blue Green | Blue | Indigo | ||||
| 绿(青) | 蓝 | ||||||
| Green | Blue Green | Blue | Indigo | ||||
中国語においては色ではなく意味合いによって表現が変わるケースが多く難しいのですが、基本的に青と緑は同じ範囲を持っているように感じられます。
それにしても、中国に習ったはずなのに、かなり違う認識になりました。
日本の「青」はどんどん細分化する道を進んでいますが、色カテゴリー名としての「青」は生きています。多くの人が藍/紺の部分を「青系」とすることに違和感を持たないと思います。古来のアヲが生きているとも言えますね。
それにしても中国語の「青」は難しいです。
チンジャオロースは青椒肉絲と書きますが、青椒はピーマンのことです。
青菜炒めは炒青菜で、青菜は主にチンゲンサイです。
「植物だと緑」のように感じますが、翻訳ソフトの回答だと「青野菜」は「绿色蔬菜」となります。


また、「青天」の日本語訳は「青空」と出てきますが「青空」の中国語訳は「蓝天」となります。「青い海」も「蓝色的大海」となります。
完全に青が蓝に置き換わった感じですね。
日本語の「青紫」も「蓝紫色」と出てきます。
辞書では「木、空、青あざ」に関しての青の用例が少しだけ出ていますが、基本的に「青」は古い言葉なのかもしれません。「青年」や「青春」といった未熟を意味する「青」はそのまま使われているようですが、色に関しては全領域で別の言葉があり、使う必要がなくなっているような感じがします。
この後、実は日本でも「青」の出現頻度は減少していきます。範囲が広く、人によって解釈が変わりそうな状況ですから、「アヲ」を使うとミスが起こりやすかったのでしょう。もっと範囲の狭い色名が必要になったのだと思います。
色々と気になることも多いですが、冠位十二階の色相を深堀りしている記事を見つけることはできませんでした。ただ、少なくとも五行説の青はGreenだったはずなのですから、冠位十二階の有力説でも大仁・小仁をGreenで表示する必要があると思いますが、「青」がBlueであることを疑うようなコメントは見当たらないです。
一人くらい緑にしていても良さそうだと思うのですが、冠位十二階の青を緑色で示している画像は見当たりません。
納得いかないですよね。
その後、何か重大な手がかりが出てくるのでしょうか。
◆まとめ
今回は冠位十二階の有力説について考察しました。
百済の博士たちの認識次第で結果が変わることだとは思いますが、ここでは「五行説の青は緑色で、百済の博士がそれをそのまま示した」「冠位十二階で青とされている冠は緑色のはず」としておきます。
また、すぐに五色を多用したかはわかりませんが、「黄」も来たのですから五行説の伝来がその後の文化に影響を与えたことは間違いありません。
次回はその後の冠位制度を見ていきます。
この辺りから色名がたくさん出てくるようになりますので、お楽しみに。
| 当記事には筆者の推察が数多く含まれています。また、あくまでもInfigo onlineに興味を持っていただくことを目的としておりますので、参考文献についての記載はいたしません。ご了承ください。 |