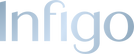日本人の青と緑⑬
二回にわたって飛鳥時代の青と緑の認識を探りましたが、今回は実際に色の確認ができる例として古墳壁画のアヲを見ていきます。文字情報が乏しいため色認識の考察は難しいのですが、実物が残っているというのは何にも代えがたく、心躍らされます。
◆王塚古墳
福岡県に装飾古墳の頂点とされる王塚(おうづか)古墳があります。6世紀中頃に造られたとされていますが、その石室の壁画は赤・黄・緑・黒・白・灰と、古墳壁画としては日本最多の6色が使われており、その出来映えは他を圧倒しています。被葬者は特定されていませんが、石室の構造により4人が埋葬されたと推定されています。
上の画像は壁画のレプリカを撮影したものです。
本物の石室は保存施設によって密閉されており、年に2回だけ一般公開があってガラス越しに見学ができるそうです。レプリカに関しては王塚装飾古墳館という古墳に隣接した施設において常時見学が可能で、ほぼ実物大の石室を体感することができます。
| 王塚装飾古墳館は今年の4月15日に火災に見舞われ、現在(2025年6月)は臨時休館しています。4月19日・20日に予定されていた古墳の特別公開も中止となりました。ただし「古墳への延焼はなく、出土品など館内の展示物にも目立った被害はなかった」とのことです。不幸中の幸いと言えるのかもしれませんが、復旧が待たれます。最新情報はこちら。 |
6世紀中頃だと百済からの使者が頻繁に来日していたはずです。特に北九州は大陸との交易の玄関口でもあるのですが、王塚古墳の壁画には五行思想の影響が見当たりません。
描かれている題材は、馬、靫(ゆぎ)、盾、刀、弓と、数種類の幾何学的文様です。騎馬は馬具まで丁寧に描かれています。ただし、高句麗時代の遺跡の壁画とかなり似ているため、渡来人の仕事だとする説も強いようです。直接教わりながら進めたのかもしれません。
緑っぽい部分の色材は緑土と呼ばれるもので、その成分は海緑石(グロコナイト)あるいはセラドナイトと考えられ、鉄を発色の主要因とする緑色顔料です。
| グロコナイト |
セラドナイト (画像: 大井町HP) |
 |
 |
冒頭で紹介した通り、壁画に使われている色は「赤・黄・緑・黒・白・灰」とされています。赤はベンガラ、黄は黄土で、黒はマンガン土、白は白色粘土です。どの「青」の部分なのかはわからないですが、実は発見当初に「青」としていた部分が、近年「灰色が変色したもの」であったことが判明したために「灰」とされています。この灰色顔料は緑土と同じ雲母粘土鉱物で、色は違っていても同じような組成の物質です。
レプリカの画像からは青系に二種類あるようには見えないのですが、いずれにしても当時は灰色顔料も緑土も「アヲ」だったはずです。
それにしても、暗闇の中で松明を頼りにこれだけの仕事をするのですから凄いですよね。
◆高松塚古墳
1972年に発見された高松塚古墳は藤原京期(694年~)に造られたもので、東西南北の壁面に陰陽五行説を元にした題材が描かれています。
被葬者については忍壁皇子(おさかべのみこ)だとする説と高市皇子(たけちのみこ)だとする説が有力で、どちらも天武天皇の皇子です。
ここで別ページに時代背景を整理しておきました。古墳築造の時期がわかるようになっていますので、是非確認してみてください。
青龍
高松塚古墳の石室には五行説にしたがった壁画があります。
東: 青龍、南: 朱雀、西: 白虎、北: 玄武というように、五行説で定められた守護が描かれていますが、もちろん今回は東壁の「青龍」に注目します。
「青龍」なのですから、この色は「五行説の青」そのものと言えます。他の撮影画像でも概ね緑に近いと感じました。顔料は岩群青(アズライト)と岩緑青(マラカイト)の混合だとされていて、局所的に青成分が強い箇所もあるようですが、現代の認識としては緑で問題ないように見えます。
西壁女子群像
有名なこちらも紹介しておきましょう。
(画像: 朝日新聞デジタル)
赤い服の人の袴は岩群青(アズライト: 藍銅鉱)、その右の緑の服は岩緑青(マラカイト: 孔雀石)だそうです。青龍とは異なり、この2色を混ぜていないということですかね。両方とも銅の二次鉱物ですが、圧倒的にマラカイトの産出量の方が多く、群青は緑青の10倍の価値があったようです。
この絵では白土も使われています。紫や黄緑、水色といった感じの色は見られませんので、五行説に従った5色(赤・青・黄・黒・白)を意図的に使用していると思います。そうしますと、群青も緑も青龍の色も「青」とみなしていたことになりそうですので、やはり「青」の認識には幅があったのでしょう。
藤原京時代もこの状態だったということになります。(前々回記事参照)
| 青(古来のアヲ) | |||||||
| Green | Blue Green | Blue | Indigo | ||||
また、群青色については中国だと青ではない可能性もあると思うのですが、どうなのでしょう。色々と大陸の文化を取り入れてはいますが、高松塚古墳壁画の色使いは日本独自のものと言えるのではないでしょうか。
― 鉛成分について ―
高松塚古墳壁画では全体的に鉛成分が多く検出されています。鉛となると、通常は赤系の鉛丹、白顔料の鉛白などが考えられるのですが、何も描かれていない箇所からも少量の鉛成分が検出されるそうです。理由はよくわかっていません。
場所も時代も全く違う話にはなりますが、あのモナリザの下地からは何種類かの鉛化合物が検出され、研究者達はレオナルド・ダ・ヴィンチが酸化鉛を使用していたと結論付けました。最後の晩餐の下地においても酸化鉛の粒子が検出されたそうです。
以前の記事でも紹介しましたが、酸化鉛は東洋において乾燥に使われることがあります。ダ・ヴィンチも乾燥促進剤として使っていたはずなのですが、自然な肌を表現するための工夫であった可能性もあるようです。
最後の晩餐
西壁女子群像でも下地に酸化鉛のようなものを塗っていたのでしょうか。もしかすると、求める効果は乾燥だけではなかったかもしれません。時代は800年も違いますが、「壁画の下地に鉛成分」という大きな共通点によって、いろいろな想像をかきたてられます。
◆まとめ_五色の青と冠位十二階の青冠
2つの古墳壁画で五行思想の影響がない「アヲ」と、影響を受けた「青」の両方を確認しました。同じ壁画でも雰囲気は全く異なりました。非常に大きな150年です。
飛鳥時代が色彩観の歴史的転換点であることがわかります。
この後、五行思想の影響はずっと日本に残っていきます。今でもたくさん確認できます。七夕の「五色の短冊」、鯉のぼりの「吹き流し」や青い鯉、相撲の土俵(土=黄)と四隅の色房など、随所に五色の名残を見ることができます。
 |
 |
これらの五色について「青は緑、黒は紫で代用されることも多い」のような表現が見られます。事実、真榊や五色幕などでは紫と緑が使われています。
「黒を紫」については美的な側面や「仏教では黒よりも高貴」というような理由によるものと考えられますが、「青を緑」については従来の「代用」という解釈はおかしいと思います。
「色材の都合で代用」という説明が見られるのですが、「群青は緑青の10倍の価値」という状況が影響しているということでしょうか?
ただ、五行説における「青」は「木・春」に対応するもので、その本質的な色相は緑色ですから五色の緑に関しては「代用」という表現は適していません。「五色の青の実際の色相は緑が中心」という理解が歴史的に正しいはずですし、青龍を見てわかる通り緑は青の一部です。
また、前回記事でも紹介しましたが、緑の単一染料はなく、緑に染めるには必ず青と黄色を混ぜていました。そうなると、むしろ染色の都合で緑を青に変えたいという状況があり得るのです。
したがって、この染色の都合を理由にして冠位十二階の青冠を青くするのはいいと思いますが、そうでなければ五行説の影響を受けたとする以上、やはり緑色で描くべきではないでしょうか。
| 当記事には筆者の推察が数多く含まれています。また、あくまでもInfigo onlineに興味を持っていただくことを目的としておりますので、参考文献についての記載はいたしません。ご了承ください。 |