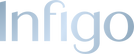日本人の青と緑⑤
前回までに古事記に登場するアヲのほとんどを紹介しましたが、時代を進める前に赤系の色についても見ていきたいと思います。
古事記には、赤・紅・丹という3種の赤系が登場します。
「紅」も「丹」も訓読みで「あか」と読むことができますから、文字の無い時代に「あか」という言葉で伝承され、編纂時に状況に応じてそれらの漢字を当てたということもあり得ます。
ですので、読み方にも注意して色名の使い分けを見ていきたいと思います。
| 説明なく日本書紀の記述・内容を添えることがあります。A/Bのようになっている箇所は、Aが古事記、Bが日本書紀になります。 |
◆赤
まずは、古事記に登場する「赤」をいくつか見ていきます。
色だけを示す「赤」の出現例は以下のような感じです。
●赤加賀智(あかかがち)・・・ホオズキ
●赤海鯽魚(あかちぬ)・・・鯛のこと
●赤色楯矛(あかいろのたてほこ)・・・赤い楯と矛
●赤幡(あかはた)・・・戦で掲げた赤い旗
ホオズキと鯛については簡単に色の確認ができますね。
赤加賀智/赤酸醤(あかかがち)は「かがち」だけでホオズキのことでした。
つまり赤加賀智は「赤いホオズキ」あるいは「赤く熟したホオズキ」といった言葉になります。


ヤマタノオロチの眼の比喩で出てくるため、「実」の方と思われます。
熟していない時期もあるので敢えて「赤い」と説明したのでしょう。
日本在来種のホオズキの熟した実はミニトマトに似た赤です。
「赤い」で全く問題ありません。
ただ、少し違った主張も見つけました。
メジロホオズキという種があり、この実はさらに濃い深紅で、良く知られているホオズキと違って萼(がく)が実を包むようなスタイルではありません。ナス科の植物だそうです。
「かがち」だけでホオズキであるのに、これに「赤」を付けて「赤かがち」とした理由は、メジロホオズキのことだったからではないかという意見でした。
メジロホオズキ

なるほど、そう言われるとこれはヘビの眼に見えてきます。
真っ赤な眼ですね。
それはそうと、赤海鯽魚(あかちぬ)というのが出ていました。
マダイをアカチヌと呼んでいたのでしょうか。
チヌはクロダイの関西名ですので、マダイが赤いクロダイと認識されていたことになります。面白いですね。
チヌという呼称もすでに奈良時代にあったのでしょうか。
| この説明のために色々と調べましたが、予想以上に大きな話になってしまったため、次回は「チヌと鯛」と題してこれを掲載することにしました。 |
マダイの色ですが、試しに下の2つの画像の魚体部分から白っぽい箇所を避けてランダムに9箇所の色を抽出し、色名検索をしてみました。
| マダイA | マダイB |
 |
 |
それぞれたくさんの色名候補が挙がっていましたが、近いと感じた2種類の名前に絞っています。
マダイA
| 乙女色,灰桜 | 聴(ゆるし)色,薄紅梅 | 洗柿,一斤染 |
 |
 |
 |
| 水柿,退紅(あらぞめ) | 紅梅色,薄紅 | 桃色,ピーチブロッサム |
 |
 |
 |
| 甚三紅(じんざもみ),ベゴニア | 柿色,人参色 | 海老赤,カーディナル |
 |
 |
 |
マダイB
| 曙色,インディアンレッド | 桃花色,薄紅梅 | 緋褪(ひさめ)色,真赭(まそお) |
 |
 |
 |
| 浅緋(あさあけ),ベゴニア | 赤蘇芳(あかすおう),栗梅茶 | 浅蘇芳(あさすおう),苺色 |
 |
 |
 |
| 蘇芳色,臙脂(えんじ)色 | 唐茶,ヘンナ | 栗梅,紅殻色(べんがら) |
 |
 |
 |
海老赤や唐茶・栗梅などの濃い色は頭部付近の色です。
生物の色は複雑ですね。
これらが集まって鯛の色。視覚は不思議です。
並べると化粧品みたいです。
どんな色名に寄っているかという意図で調べてみましたが、思ったほど重複していませんでした。
ただ「紅」が6回、「蘇芳」が3回出てきています。
「紅」についてはこの後に紹介しますが、「蘇芳(すおう)」は植物の名称でした。
インド・マレー原産で、奈良時代に渡来したそうです。
花蘇芳

(画像提供:庭木図鑑植木ペディア)
花は桃色ですが、この木の心材に赤の成分があり、これをアルカリ性にして定着させると蘇芳色になるのだそうです。
画像から抽出された色に「普通の赤」はないですし、どちらかと言えばピンクなのですが、やはり我々は「鯛は赤い」と考えます。
「赤海鯽魚」の色も「赤」で適切です。先の表にも「赤」の字は1つしか出てきていないのですが、それでも赤ですよね。
今回のケースでは「黒いチヌに対しての赤チヌ」なのですから「赤系であること」以外の情報を含める必要はありません。色グループ名としての「赤」の価値はこういうところにありますね。
その後、色名が豊かになると産卵期の鯛は桜鯛と表現されるようになります。
比較的若い春の鯛はマダイAのようにピンクなのですが、色も季節も「桜」という1字に託すというのはとても日本的ですね。風情のある表現だと思います。
そもそも、現代でも赤は青に負けず劣らず特殊です。
「赤」を国語辞典で調べると「緋・紅・朱・茶・桃色などの総称」のように書かれています。古語辞典の記述ではありませんよ。
「赤」に限らず、全ての色名は対応する色相にある程度の幅があって当たり前ですが、それにしても幅が広いです。他の色より細分化されているとも言えるのでしょうか。とにかく種類が多いような気がします。
ただ、幅広いとは言え、ほとんどの人にとって茶色と赤は全くの別物です。また、ピンクが赤系だと感じてはいますが、ピンク1色のものを「赤い」とは言いません。
つまり、「赤」は大きな色グループの名称であると同時に、ある程度範囲を絞った色名としても使われていることになります。
古事記に描かれているような時代ですと、茶色だけでなく黄色も色グループとしては「アカ」なのですから、とんでもない勘違いを起こす可能性があります。
ですから先入観を捨て、丁寧に考える必要があると思いますが、赤加賀智も赤海鯽魚も「赤」で何の問題もありません。
「赤」ではもう一つ、「赤色楯矛」をピックアップしておきます。
赤い楯と矛というそのままの意味ですが、これはパンデミックのお話に出てきます。
日本書紀の記述も踏まえて大筋を紹介します。
即位が紀元前97年とされる崇神天皇の治世に、人口の半分以上が失われるような疫病の大流行がありました。
ある夜、悩む天皇の夢枕に大物主大神(おおものぬしのおおかみ)が現れ、「これは私がしたことだ。意富多多泥古/大田田根子(おおたたねこ)をもって私を祀れば、病は止み、国は安らかになるだろう。」と告げます。
天皇はこの人物を探し出させ「汝は誰か」と質問したところ、大物主大神の子孫だとわかります。
天皇は非常に喜び、大田田根子に大物主大神を祀らせることになるのですが、これが大神神社(日本人の青と緑③でも紹介)の始まりとされています。
つまり、大田田根子は大神神社の初代神主ということになります。
さらに、「墨坂の神」に赤色楯矛/赤盾八枚・赤矛八竿を祭り、 また「大坂の神」に黒色楯矛/黒盾八枚・黒矛八竿を祭るよう命じます。これを遂行してようやく疫病が終息したそうです。
日本書紀ではこの指示も大物主大神のお告げによるものとされています。
「墨坂の神」は宇陀にある墨坂神社、「大坂の神」は奈良県と大阪府の境界にある大坂山口神社になります。当時この二か所は交通の要衝であったそうで、疫病の侵入を防ぐという意味で非常に理にかなったお告げだと感じます。
墨坂神社では、新型コロナウィルス感染拡大の際、修復しながら使い続けている「赤盾八枚・赤矛八竿」を拝殿に掲げるようにし、さらに「新型コロナウイルス平癒祈願祭」を執り行ったそうです。
日本最古の健康の神としての責任感が感じられますね。

墨坂神社Facebookより
上の画像で盾と矛が確認できます。
こちらも「赤い」で問題ありませんね。
矛に付いている旗と比べますと、盾の赤は特徴的な塗料を使っているようにも見えます。
なお、赤幡(あかはた)という赤い旗については色のヒントが全く無かったのですが、この記述では「丹の緒」と「赤の旗」というように色が区別されていました。
この「丹」については古事記の赤(下)で紹介します。
◆紅
次は「紅」について考えます。
前回記事の「紅紐つけし青摺衣」のところで出てきましたが、古事記にはこのフレーズでしか「紅」は登場しません。
「紅」の原料はベニバナという植物です。
この花から赤い成分を取り出し染料とするのです。
奈良県の纏向遺跡において、3世紀中頃の溝から大量のベニバナの花粉が発掘されているそうなので、少なくともこの時期までに抽出⽅法も含めてベニバナが伝来していたことになります。
仁徳天皇の治世は4世紀末~5世紀前半ですから、「紅の紐」という表現に時代的な矛盾がなかったことが、纏向遺跡での発掘によって初めて確認されたと言えます。
まず、色相の前に、この「紅紐」を何と読むかが問題です。
現代語訳を見ても定まってはいませんが「あかひも」が多いように思います。
どうやら「べに」という言葉はこの時代にはなかったようですので、「紅」の読みは「くれない」か「あか」ということになります。
そうすると「ベニバナ」がどうなっていたのかが気になるのですが、その呼称には
呉の藍(くれのあゐ)→呉藍(くれあゐ)→くれなゐ
という変遷があり、元々この植物が「くれなゐ」と呼ばれていたのだとわかりました。
(平安時代まで「い」と「ゐ」は区別していて発音も違いますので、当時の読みを示す場合は「ゐ」と表記します)
この呉(くれ)とは三国志で有名な魏・呉・蜀の呉(ご)のことです。
つまり、纏向遺跡での発掘により、3世紀中頃に呉からベニバナが伝来していたということが確定的なのです。
仁徳天皇よりもずっと前にそのような外交があったのは驚きです。纏向遺跡の調査の価値ももの凄いですね。
以上のことから、奈良時代までに「紅い(あかい)」という表現が生まれていたとしても、仁徳天皇時代の「紅」の読みが「くれあゐ」か「くれなゐ」であった可能性が高いことがわかります。
ただし、「紅」が「くれなゐという色」という意味の、完全なる色名として使われているかはわかりません。「呉藍で染めた」という染料の情報を含めただけとも考えられます。
そうすると「あかひも」と読ませて原材料の情報を「紅」という字に託したという可能性も出てきます。
「紅という色」と「紅の色」とでは、意味が全く違うのです。
7:3くらいで「紅という色」つまり色名になっているとは思いますが、どちらにしても「くれないのひも」と読むことに支障はないですよね。
紅紐の「紅」の色候補として3種類挙げてみます。
| 薄紅 | 中紅 | 紅 |
 |
 |
 |
鮮やかな色ですが、派手な感じも無く綺麗ですね。
4~5世紀に右の「紅」のような色が出せたかはわかりませんが、「中紅(なかくれなゐ)」くらいであれば可能だったのではないでしょうか。前回記事でもこれを推しました。
紐であれば綺麗にムラなく染まったと思います。
なお、ベニバナの染料は貴重であったため、この3種については平安時代に一般の使用が禁じられたそうです。
貴族だけの色になったということですね。
◆まとめ
今回は古事記の「赤」と「紅」について見ていきました。
「赤」は問題のない使い方しか見当たらず、黄色や茶色を「赤」としているような例はなさそうでした。
奈良時代には「黄」も「茶」もありますので、黄色い物をアカいと表現して読者を混乱させるようなことはできなかったということかもしれません。
「紅」は呉(ご)からのベニバナ伝来で生まれた色でした。
初めて鮮やかに染まったとき、身震いしたに違いありません。
「紅は赤の一種」といった概念があったことを示すような表現は見当たりませんでしたが、概ねピンクで普通の赤が無いマダイを「赤のチヌ」としているのですから、「赤系」という色グループを表す意図が少なからずあったと思います。
ただし、この記事をまとめるにあたってマダイが英語でred sea breamだということを知りました。
結局世界的に赤いとされているのですから、いかにピンクの成分が多かったとしても、茶系も合わせて遠くから見ると当たり前のように赤に見えるのではないかと思いました。
ただ、「赤」という言葉の包括的な表現力や柔軟性を示しているということも言える気がします。英語のredについても似たような現象があるようで、かなり広い色相においてredが出てくるようです。
全世界的に「赤」はお祝いの色であり、血の色ですので、どの国でも他の色とは全く違う扱いになっているのかもしれません。
次回は「チヌと鯛」についての調査報告をします。
「青」とは全く関係ありませんが、お楽しみに。
| 当記事には筆者の推察が数多く含まれています。また、あくまでもInfigo onlineに興味を持っていただくことを目的としておりますので、参考文献についての記載はいたしません。ご了承ください。 |