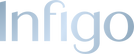日本人の青と緑⑭
前回は古墳壁画を紹介しましたが、色名についての考察は文献が頼りです。
ただ、飛鳥時代以降ですと新色の登場は色制の記述に偏っています。
冠十九階までを⑪と⑫で紹介しましたので、さらにその後の色制を探るべく日本書紀の終盤の記述を見ていきます。
◆7世紀の色制
まずは冠位十二階から始まる7世紀の色制について整理しました。
以下のように推移します。
冠位十二階(603) → 七色十三階(647) → 冠十九階(649) → 冠位二十六階(664) → 冠位四十八階(685) → 持統天皇の詔(690)
残念ながら冠位二十六階の記述には色名が出てきませんが、天武天皇が制定した冠位四十八階の記述では色名が出てきます。さらに、名称はないのですが、冠位四十八階の色を改定するような形で持統天皇が詔を出していて、ここにも色名が出てきます。
この二つの制度で使われた色を見てみましょう。
冠位四十八階(諸王十二階と諸臣四十八階)
この制度では諸臣四十八階という通常官職の上に、諸王十二階という皇族用の冠位が設けられました。上位の色から挙げていきます。
諸王:朱花
諸臣:深紫、浅紫、深緑、浅緑、深蒲萄、浅蒲萄
朱花は「はねず」と読みます。朱華や唐棣色とも書かれます。
これが紫よりも上位の色だったことになりますが、奈良時代になると黄丹(おうに)と呼ばれる色が皇太子の服に使われました。この色は今でも使われています。
| 朱花 | 黄丹 |
| #f4a57a | #ee7948 |
レシピは基本的に同じで、いずれも支子(くちなし)に紅花です。
| ベニバナ | クチナシ |
 |
 |
現代でも皇太子は黄丹袍(おうにのほう)を着用します。
 |
| 皇太子徳仁親王(現天皇陛下)と皇太子妃雅子(現皇后陛下)の結婚の儀 1993年6月9日 |
(画像: 外務省ホームページ)
蒲萄は「えびそめ・えびぞめ」と読むそうで、山ぶどうの色を表しています。赤味を帯びた紫色です。
また、蒲萄=葡萄だそうです。葡萄はブドウと読みますね。
ブドウのツルがエビのひげのように巻いていることから、ブドウは「エビ」と呼ばれていたそうです。
葡萄色(えびいろ)はこのような色になります。
| 葡萄色 |
| #640125 |
持統天皇の改定
天武天皇の制度は持統天皇によって改定されました。
諸王:黒紫、赤紫
諸臣:赤紫、緋、深緑、浅緑、深縹、浅縹
「紫 緋 緑 縹」つまり「紫-赤-緑-青」という序列は冠十九階の順番に戻った感じになります。持統天皇は冠十九階の色制に何らかの合理性を感じ、倣ったものと思われます。天武天皇の時の紫と葡萄色は似ていて非常にわかりづらかったはずですから、妻としてひそかに不満に思っていたのかもしれません。
なお、この記述が縹(詳しくはこちら)の文献初登場です。
| 浅縹 | 縹色 | 深縹 |
| #84B9CB | #0074A0 | #1D3156 |
2種類の制度を紹介しましたが、どちらにおいても「赤」や「青」という表記はありません。この傾向は冠十九階からずっと続いています。
現在であれば、他に似た色が使われない以上、「緋」や「朱」のところは「赤」と表記されるでしょうし、「縹」のところは間違いなく「青」となるはずですので、この事実は「赤」「青」の持つ色グループ名としての性質が極めて強かったことを示しています。
緑も縹も青であったことを踏まえると、当時においては極めて自然なことだったのでしょう。赤も青も、色味の指示をする際に使用できるような言葉ではなかったのです。
◆7世紀の「青」
ここでは日本書紀に出てくる7世紀の「青」を紹介します。日本書紀の最後は持統天皇紀になります。
青霧_皇極天皇紀 (在位: 652-645)
青油笠_斉明天皇紀 (在位: 655-661)
御青飯_持統天皇紀 (在位: 690-697)
青霧
青霧はそのまま「青い霧」という意味で、凶兆とされていたようです。
「青い霧が地面いっぱいに湧き上っていた」と書かれているのですが、これは空が青い理由として知られるレイリー散乱のようなことですかね。空気の分子が波長の短い青と紫の光を散乱することで、遠くの山が青く見えたりします。
霧が完全な青になるはずはありませんので、こんな感じでしょうか。湿度が高い時はレイリー散乱があっても多少白くなるはずです。

7世紀になってもこの「漠」の感じは青なのでしょうか。
皇極天皇が即位してからの記述では、悪天候や日蝕、あるいは虫の大量発生や火事のこと、そして百済や高麗の乱れなど、悪いことばかり書き連ねて不穏な空気を醸し出しています。
その後、即位2年に蘇我入鹿の謀略により山背大兄王子が自殺し、その7か月後に乙巳の変が起こって蘇我宗家は滅亡します。
青油笠(あおきあぶらぎぬのかさ)
どういった感じの物かはよくわからないのですが、これは雨具だそうです。
斉明天皇が即位した655年の記述に、唐人のような風貌をした人が、この雨具をかぶって竜に乗って飛んでいたというお話が唐突に出てきます。油笠というのは笠に油を塗った物のようで、唐では桐の油を使った防水技術が発達していたそうです。
斉明天皇は前述の皇極天皇と同一人物で、乙巳の変を機に一度譲位して再び即位しました。
| 皇極天皇 (斉明天皇) |
 |
| 三英舎 「御歴代百廿一天皇御尊影」 PD |
この雨具の何が青いのかはよくわかりません。青く染めた繊維で作った笠かもしれませんし、油を塗って青い光沢が現れたのかもしれません。
このファンタジーはその6年後の斉明天皇崩御の伏線になっているようです。
百済復興に向けた戦に備えるため、斉明天皇自ら661年に今の福岡県に出向くのですが、その後わずか数か月で亡くなってしまいます。
最後は朝倉橘広庭宮(あさくらのたちばなのひろにわのみや)という場所に移っていたのですが、「朝倉の社の木を伐採してこの宮を作った。それで神が怒り雷で殿舎を破壊した。また宮中に鬼火が現れ、周囲の人々の病死が多かった。」とあります。
その翌月に斉明天皇崩御となるのですが、「朝倉山に鬼が出現し、大きな笠を着て葬儀を見ていた」と書かれているのです。これは「青油笠」と関係がありそうですね。
朝倉の社というのは現在の福岡県朝倉市にある麻氐良布(まてらふ)神社のことで、御神体である麻氐良山(までらやま)の木を伐採するのが良くなかったのでしょう。神聖な土地を荒らしたことが死因だと、謎の鬼を使って示しているのです。
| 麻氐良布神社(上宮) | 麻氐良山 |
 |
 |
山頂にひっそりと鎮座する麻氐良布神社の主祭神は伊弉諾尊(いざなぎのみこと)です。こう見えて式内社なのですが、現在の社殿は江戸時代のものです。
ここは戦国時代に城が築かれ、戦の最前線となっていました。その後、城主の秋月種実が豊臣秀吉に降伏し、社地が没収されたことで荒廃してしまったのだそうです。
日本書紀においては斉明天皇が次々に宮を造営したことや、香具山の西から石上山までの巨大運河建設などについて批判的な記述も見られます。天皇に関するネガティブな記述はかなり珍しいと思いますが、多くの市民を巻き込んだことへの異議を示したかったのでしょう。
しかしながら、昨今の斉明天皇の評価は異なっており、発想豊かで先見の明があったとする研究者も多いようです。死因の設定も怪しいですし、ジェンダーギャップがあったように思います。
御青飯
これは「ひじきおぼの」と読むそうで、天皇崩御後にご遺体を安置する殯宮(もがりのみや)に供えられたお供物の一つです。
686年9月に天武天皇が崩御されたのですが、688年11月に埋葬されるまでの間、ずっと殯宮に安置され、泣き悲しむ儀式が定期的に執り行われていました。御青飯が出てくるのは687年8月の記述になります。
御青飯というのは「青菜ご飯」といった感じのものではないでしょうか。
青い器にご飯を盛ったものという説もあるようですが、青磁の伝来は11世紀頃と言われてますし、この青は植物の青と考えて問題ないと思います。
天武天皇は「大内陵」に埋葬され、702年に崩御された持統天皇がその翌年に合葬されています。
| 天武・持統天皇陵 檜隈大内陵(ひのくまのおおうちのみささぎ) |
 |
| 奈良県高市郡明日香村 |
◆まとめ
今回は日本書紀の最後の方の色を追ってみました。
これで「色のアラカルト」では7世紀までの青のほとんどを見てきたことになります。
今では縹という言葉が使われることはほぼありませんが、色名としての現代の青は縹が一番近いと思います。
また、7世紀の「青」は色名というより色グループ名の性質が強いように感じました。色を使った制度の記述に登場しないのですから、青の色域の広さは十分に理解されていたのだと思います。
また、今回の例では暗示の手段として「青いもの」が出てきました。色自体からは少し離れた別の意味合いが存在し、不穏・不吉といった様子を表現するのに「青」が便利だったのかもしれません。「漠」のもやっとした感じが生きているように思います。
| 当記事には筆者の推察が数多く含まれています。また、あくまでもInfigo onlineに興味を持っていただくことを目的としておりますので、参考文献についての記載はいたしません。ご了承ください。 |