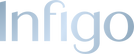日本人の青と緑④
前回までに神話のアヲを紹介してきました。今回も古事記に出てくるその後のアヲを見ていきます。
次は天皇記となるのですが、色としての「青」の出現は以下の通りです。
●神武天皇記・・・青雲之白肩津
●垂仁天皇記・・・青葉山
●倭建命の歌・・・青垣
●応神天皇記・・・竹葉青
●仁徳天皇記・・・青摺衣、青菜、あをによし
●雄略天皇記・・・青摺衣
◆青雲(あをくも)の白肩津(しらかたのつ)
白肩津というのは地名です。
神武東征における近畿への上陸地(現在の東大阪市日下町)です。
| 即位前の神武天皇は、古事記において神倭伊波禮毘古命(かむやまといわれひこのみこと)、日本書紀において神日本磐余彦火火出見尊(かんやまといわれびこほほでみのみこと)と表記されていますが、ここでは便宜上「イワレビコ」と表記します。 |
イワレビコの軍は上陸後に那賀須泥毘古(ナガスネヒコ)との間で非常に長い広範囲での戦となりますが、これに勝利してイワレビコは神武天皇として即位することになります。これが紀元前660年とされています。
東大阪市日下(くさか)町は大阪港から20km以上離れているのですが、縄文時代初期は氷河期が終わって温暖化に向かう時代のため、海面上昇が起こり現在の河内平野の奥まで海に浸かっていたことがわかっています。
この湾は河内湾と呼ばれていますが、縄文時代中期になると海は退きはじめ、川が土砂を運びこんで河内湾を埋め立てていきました。そして河内湾の入口はどんどん狭くなり、弥生時代には湾の入口が塞がって湖になりました。
この湖は河内湖と呼ばれています。
 |
 |
| 約5500年前 | 約2000年前 |
この河内湖周辺には遺跡がたくさん見つかっていて、この湖ができたことで相当な人口増加があったとされています。漁業が盛んであったこともわかっています。
その後、仁徳天皇は即位の際にこのエリアに都を遷し(難波高津宮)、治水を頑張ります。
こうして、この地域はさらに栄えることになります。
大阪発展の原点にはこうした歴史があったのですね。
日下町の位置に合わせるとこのような感じです。

「青雲」というのはどうやら「白肩津」の「白」に対する枕詞のようで、特に意味はない可能性もありますが、白の対比として「青雲」が出てきたのは面白いです。
「青雲(せいうん)」はお線香でも有名ですが、調べてみますとこのような意味がありました。
A.青みがかった雲。また、よく晴れた高い空。青空。
B.地位や学徳の高いことのたとえ。
C.俗世間を離れ、超然としていることのたとえ。
また「青雲(せいうん)の志」という表現もありました。
青雲の志:功名を立て、立身出世をしようとする志。
これは、王勃(おうぼつ)という7世紀中頃の唐の詩人の表現で、青雲自体は「空に浮かぶ青い雲」という意味です。
Bは「青雲の志」から来ていますね。
CはBの派生形でしょうか。あるいは神武東征から来ているのかもしれません。
ここでの問題は、Aの「青みがかった雲」です。どういう色でしょう?
青雲(あをくも)は、訳すとすれば上記Aのような「アヲい雲」あるいは「アヲい空に浮かぶ雲」ということになります。
前者の「アヲい雲」の場合、白との対比で出てきたのですから、灰色がかった色、まさに「漠」のアヲだと考えることができます。

初回記事で使った図です。
もはや色相に関係なく、明度の高低で決まるアヲですので、敢えて赤系の図にしました。
シロとアヲの対比がわかります。
また、後者の「アヲい空に浮かぶ雲」だとすると空自体の色がアヲということになりますが、「青雲」は「日没後に僅かな時間見える青い空に浮かぶ雲」のことで、イワレビコ軍が日没の時間帯に到着したのではないかという主張も見つけました。
Aの意味に青空というのもありましたが、やはり研究者の方々はアヲが「青い色」とは考えづらいのでしょう。
そうしますと、雲の色であっても空の色であっても「青雲」のアヲは灰がかった「漠」のイメージに近づきます。

万が一、太安万侶が「青雲の志」を知っていたとしても、「青雲の白肩津」の「青」は「青い色」ではなく「漠」をイメージしていたと考えたいです。
◆紅紐(くれなゐのひも)つけし青摺衣(あをずりのころも)
「紅紐つけし青摺衣」は天皇の家臣が着ている装束で、仁徳天皇のお話と雄略天皇のお話で登場します。
仁徳記では、雨水で滲み服のアヲの部分が紅色に変色したという描写が出てきますので、「紅紐」は赤系の染料が使われている紐だということがわかります。「紅」が色名として使われていることも間違いありません。読みは「アカ」であった可能性もあります。
古事記には赤・丹・紅と赤系の色が3種類出てきますが、こちらもいろいろと事情がありそうですので「アカ」については次回考察することにします。
青摺(あおずり)というのは山藍の葉などで模様を青く摺り出すことなのですが、山藍の葉だけで染色すると、青色の色素が含まれないので緑色にしかならないそうです。
青摺については染色技法の記録がなく、当時の色の正確なことはわかっていませんが、山藍の茎と根は青色の成分を含んでいるそうで、それにより推察がさらに難しくなっているみたいです。
ただ、今なお「山藍摺」という色名が残っています。
統一はされていないようですが、全てこのような灰色がかった色でした。

「紅」がつく色の中でも一番落ち着いた感じの「中紅(なかくれなゐ)」という色と合わせてみます。

渋いですね。
厳かな感じがします。
その後、青摺の衣は祭事や神事で使われるようになり、今でも様々な儀式で見られます。
下の画像は伊勢神宮の「一月十一日御饌(みけ)」で奏行される「東遊(あずまあそび)」という歌舞の光景です。
まさに「紅紐つけし青摺衣」を見ることができます。
(画像提供:神宮司庁)
光の加減かもしれませんが、青摺の部分は前述の山藍摺の色よりも普通の緑に近いです。
つまり、葉っぱ成分だけだとみなされていることになります。


古事記によると、仁徳天皇の在位は394年~427年、雄略天皇の在位は456年~479年です。
この色は1600年前のアヲということになりますね。
◆あをによし
「あをによし」は奈良の枕詞として有名ですが、古事記にも出てきています。
漢字では「青丹よし」と書くようで
①青丹=岩緑青(孔雀石=マラカイト)で、奈良が産地として有名
②平城京の丹塗りに、木々の緑が映えている
この2通りの説が有力だそうです。
ただ、古事記においては②のような時系列が崩れる言葉は使いたくないはず(前回記事「蒲黄」参照)ですので、岩緑青の説を支持したいです。
そうなると、こうした完全な緑色です。
マラカイト
ただ、今なお「青丹」という色がありました。
元々は「青土」と書いて「あをに」と呼んでいたらしく、このような色になっています。
「灰がかった緑」という感じですね。
◆その他のアヲ
「青葉の山」は垂仁天皇記に、「竹の葉が青いように」というような比喩が応神天皇記に出現します。
また、仁徳天皇記には「青菜」と出てきて、今と変わらず野菜の名称でした。
いずれも葉緑素の緑をアヲと形容していますね。
また、倭建命/日本武尊(ヤマトタケル)が
「倭は国のまほろば たたなづく 青垣 山隠れる 倭し麗し」
(やまとはくにのまほろばたたなづくあをかきやまごもれるやまとしうるはし)
と歌ったのは非常に有名です。
この青垣は前回記事で紹介した青垣と同じ山々を表しており、この歌は
「大和は国の中で一番良いところである。幾重にもかさなりあった垣根のような山々にかこまれた大和はほんとうに美しくて立派なところだ」
という意味になります。
ヤマトタケルは蝦夷を平定して帰ってくる途中に伊吹山の神を討ち取ろうとしますが、神の怒りを買い、傷ついて山中をさまよいます。
そして今の三重県亀山市にあった能煩野(のぼの)という場所にたどり着き、心身ともに疲れ果てた状態で上記の辞世の歌を残し、この地で亡くなりました。
宮内庁によりヤマトタケルの墓に治定されている能褒野王塚古墳は三重県で最大の前方後円墳になります。
その他にも関連史跡が数多くあり、ヤマトタケルの妃である弟橘比売命/弟橘媛(オトタチバナヒメ)生誕の地ということもあって、ここは伝説の伝承地として広く知られています。
 能褒野王塚古墳 |
 能褒野神社拝殿 |
◆まとめ
古事記のアヲを全て見てきましたが、基本的には植物の緑でしたね。
また、漠のアヲも出てきました。
青雲(あをくも)のアヲは灰がかった色の可能性が高いと感じます。
古事記のアヲについて総括しますと
アヲ=緑寄りの(青~緑)+灰がかった色
ということになるかと思います。
チラッと予告もしましたが、次回は気分を変えて古事記に登場する赤系の色について考察します。
お楽しみに。
| 当記事には筆者の推察が数多く含まれています。また、あくまでもInfigo onlineに興味を持っていただくことを目的としておりますので、参考文献についての記載はいたしません。ご了承ください。 |