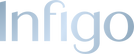日本人の青と緑⑨
前回は丹土、鉛丹、辰砂を紹介しました。
今回は丹塗りの実例を見ていきながら、「バーミリオンが朱色」「鉛丹の色がオレンジ」という前回生じた疑問についても考えます。
◆丹生都比売神社
前回、真田信繁の拠点が辰砂の産地に近かったと紹介しましたが、その地には世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の登録資産でもある丹生都比売神社(にうつひめじんじゃ)があります。
御祭神は丹生都比売大神という天照大御神の妹神で、魔除けの丹をつかさどり、あらゆる災厄を祓う女神として崇敬されています。
古代からこの地に住み辰砂を扱っていた丹生氏は丹生都比売大神を祭祀する神官になりました。水銀の精錬技術を持つ秦氏が大陸からやってきたからです。丹生氏のポジションは名誉職のような感じですかね。
秦氏は真朱も銀朱も自在に製造していたと思います。
丹生都比売神社のHPに「丹」とは、辰砂(朱砂)の鉱石より採取される赤い顔料を表すと書いてあるくらいですから、本朱(便宜上、今回の記事では真朱も銀朱も本朱とします)が使われているはずです。
丹塗りは光の加減でかなり印象が変わるため、画像から結論付けることはできませんが、本殿の柱や階段は本朱だと思います。
本殿
(画像:丹生都比売神社HPより)



実際に絵具で塗った本朱も載せておきます。
左から真朱、鎌倉朱、赤口本朱ですが、柱は鎌倉朱と赤口本朱の中間といった感じがします。
間近で見て色を確かめたいですね。

この神社の鳥居は本朱ではないですね。
鉛丹主体でしょうか。あるいは全然違う色材かもしれません。
◆鶴岡八幡宮
「鎌倉朱」という絵具がありますので、鶴岡八幡宮を見てみましょう。
楼門
 鎌倉朱
鎌倉朱
どうでしょう。これはかなり近いですね。
楼門と舞殿
舞殿も全く同じ色にしていると思います。
やはり「鎌倉朱」というのはこの色から来ているのでしょう。
昔からある絵具でしょうから、色が常に継承されているということもわかります。
改めて社殿も確認したいです。
◆興福寺中金堂

2000年から解体・調査が始まり2018年に落慶した興福寺中金堂の柱には本朱が使われていると思われます。
この再建においては「出来得る限り古式の工法を採り入れた」そうなので、丹塗りに関しても奈良時代に使ったであろう色材を選択したはずです。
色は「赤口本朱」に近い感じでしょうか。
少しだけ黄色や茶色が入っている気もします。 赤口本朱
赤口本朱
「古式」という事で鉛丹は使われていないはずですから、銀朱の水銀成分だけの黄色みなのでしょうか。
ただ、そうするともっと鮮やかになると思うのですが、かなり落ち着いた色です。
他に考えられるのはベンガラの黄色成分(Fe2O3·H2O)ですかね。
本朱に明るめのベンガラを混ぜるとこういう感じになるのかもしれません。
◆春日大社
春日大社では本殿が本朱、中門や回廊などは鉛丹だそうです。
丹生都比売神社もそうですが、環境に配慮して最重要箇所だけに抑えているのかもしれません。
本殿
(画像:春日大社HPより) 真朱
真朱
本殿では本朱3割・鉛丹7割の塗料を塗り、その上から本朱10割を塗っているそうです。本朱10割というのは現代ではかなり珍しいことのようです。
この「本朱」というのは「真朱」という意味で使っている言葉かもしれません。
相当近いと感じますので間近で見たいところです。
なお、奈良には大和水銀鉱山と呼ばれる辰砂の産地があり、昭和46年に閉山するまで掘られていました。
万葉集にも
「山跡之 宇陀乃真赤土 左丹著者 曽許裳香人之 吾乎言将成」
=大和の 宇陀の真赤土(まはに)の さ丹つかば そこもか人の わを言(こと)なさむ
という歌があります。
「宇陀の赤土の丹が(顔に)ついたならば、たったそれだけのことで、世間は私のことをとやかく言うのでしょうか」といった意味になります。
「真赤土のさ丹」は「赤土の辰砂」という意味なので、このときすでに「丹=土」ではないこともわかります。
中門と回廊

こちらは鉛丹です。鉛丹は自然光の中で明るい表情を見せます。
やはり「鉛丹色」として紹介していた色よりも実際の色は明るく感じます。

また、前回記事の段階で鉛丹の絵具の色と「鉛丹色」との大きな差が気になっていましたが、どうやら四酸化鉛(Pb3O4)の純度の問題のようで、この純度が高いと赤みが増すそうです。
同時に生成される一酸化鉛(PbO)のβ型が黄色っぽく、これの割合が上がることでオレンジになるのかもしれません。
この物質は金密陀(きんみつだ)とも呼ばれ、これ自体が黄色の顔料として使われていた時代もあるそうです。
飛鳥時代には、この金密陀を用いた「密陀絵」という特殊な絵画技法が大陸から伝来しました。密陀絵とは、金密陀を乾燥剤として使用し、亜麻仁油などの乾性油と混ぜて絵具を調合した後、絹や木の表面に塗布して乾燥させることで図柄を定着させる方法です。「東洋の油絵」ということになるのですかね。
| 唐人物密陀絵盆 江戸時代・18世紀 |
花蝶密陀絵膳 江戸時代・19世紀 |
 |
 |
(出典:ColBase)
絵具ではこの金密陀の影響が減らないと赤みが出てこないのだと思いますが、高純度Pb3O4の赤絵具は見つかりませんでした。
ひょっとすると絵具を加熱することで赤くなるかもしれません。
3PbO + 1/2O₂ → Pb₃O₄
...なので可能性はあるような気がします。
ただし、鉛は気軽に扱って良い物ではありません。絵具以外では純度95%を超えるような製品もありましたが、入手するのはやめました。危険なので上記の加熱実験もできません。
鉛含有塗料は、相当前から塗装作業者の健康被害が問題となっているらしく、日本塗料工業会という社団法人が2020年に会員企業による生産・販売の完全終了を宣言していました。ただ、この発信には法的拘束力はなく、自主規制に任せた状態のためこの団体と無関係な企業であれば普通に鉛丹製造が可能です。
国際的にも鉛含有塗料の撤廃が叫ばれており、先進国の中で法的規制がないのは日本と韓国だけだそうです。有害とわかっていながら国が踏み込んだ規制に踏み切れないのは、丹塗りの伝統継続のためなのでしょうか。鉛丹色は伝統色なので確かに難しい問題です。
ただ、生産・販売と購入・使用に関して何らかの規制は必要だと思います。世界的問題になっている中、Amazonで錆止め鉛丹塗料を普通に買えてしまうのはおかしいですよね。伝統継承のためにも、きちんとした規制が望まれます。
そのようなこともあってか、春日大社の中門の方の手前にある柵は合成樹脂だそうです。頻繁に塗り替えるからだと思います。
◆伏見稲荷大社
伏見稲荷大社の千本鳥居は純粋な鉛丹塗装のようです。
鮮やかさを出しつつ長持ちさせるために五度塗りしているそうです。
伏見稲荷大社千本鳥居
ただ、鉛丹問題は神社にとって厳しい話ですね。
今後もこれを続けられるのでしょうか。
この美しさは鉛丹あってのものでしょうから気掛かりです。
◆厳島神社
厳島神社の大鳥居は9代目で1875年(明治8年)に再建されたものだそうです。当時は神仏分離令の影響で「朱色は仏教的」とされたために白木のままだったそうですが、1909年(明治42年)の修復では丹塗りされました。
前回修復の完了は2022年です。修復前が鉛丹で、前回修復時には有機質の顔料が使われたそうです。新しいタイプの「丹」ということになります。
大鳥居(修復前) 鉛丹
大鳥居(修復後) 有機顔料
この鳥居は海に浸かりますから、特にダメですよね。
今後はこうした安全と環境に配慮した丹塗りが増えていくのでしょうか。
経年変化の度合いがわからないので何とも言えませんが、色味はかなり変わっていますね。赤みは抜けていく計算なのでしょうか。
◆最上稲荷山妙教寺
岡山にある最上稲荷山妙教寺(さいじょういなりさんみょうきょうじ)という日蓮宗のお寺には大きな鳥居があり、これにはベンガラが使われています。
最上稲荷大鳥居
(提供:岡山観光WEB)
凄い大きさですね。
神仏分離令の際に「神仏習合」の祭祀形態が許された、数少ない貴重な寺院だそうです。
このお寺から50kmくらい離れた吹屋という地区は「ジャパンレッド発祥の地」として日本遺産に登録されています。
吹屋は江戸時代からベンガラと銅が出る鉱山町として繁栄し、ベンガラは1970年まで製造されていました。
今でもその町並みが1.5kmくらい続いているそうで、伝統的建造物群保存地区に定められていて一面ベンガラ塗装です。
懐かしさを感じる色です。
吹屋ベンガラは銅山からの副産物である硫化鉄(FeSやFe2S3等)を原料として人口的に製造されたものでした。硫化鉄を焼いて中間生成物の淡青色のローハ(硫酸鉄水和物FeSO4·nH2O)というものを作り、これを酸化してベンガラ(Fe2O3)を生成するそうです。
ベンガラは水銀朱の代用として古くから丹塗りに使われてきたそうです。水銀朱は非常に貴重で、広い面積を塗るのは無理だったのでしょう。
藤原頼通が建立した平等院鳳凰堂はベンガラで塗られていましたが(前回記事参照)、もしも道長の計画であったならば、強引に真朱100%が指示されていたかもしれません。
ベンガラは環境にも優しくローコストのため、今でも色々な方法で丹塗りに使われています。本朱や鉛丹に混ぜて、色の調整に使うことも多いようです。
黄色みを加える工夫次第では、鉛丹の完全な代替になる可能性も秘めていると思います。令和の時代に人類最古の顔料が脚光を浴びるという劇的な展開が待っているかもしれません。
◆色材の多様化
丹塗りは本朱、鉛丹、ベンガラを使い分けたり、これらを混ぜて色を調整したりして行われています。
厳島神社のように新しい色材が使われたりもします。
確かに色味も様々です。色味を維持・伝承するためにそれぞれで様々な努力をしているのだと思いますが、マニュアルなどは存在していないようなので、正確な情報がなかなか見つかりません。
| 薬師寺 西塔 | 元乃隅神社 |
 |
 |
 |
 |
| 貴船神社 | 富士山本宮浅間大社 |
真朱の場合は間近で見るとわかるかもしれませんが、色材の特定は簡単ではないです。
◆朱色の認識について
ここで、バーミリオン(銀朱)の日本語名が「朱色」となった経緯について考察します。
そもそも朱色は真朱であったはずなのに、なぜ少しズレることになったのでしょう?
前回記事の内容も踏まえ、古代から整理しつつ考えていきます。
元来「丹」は土を指す言葉で、黄土や赤土を表していましたが、やがて赤土、ベンガラ、辰砂などの赤い顔料だけを指すように意味が変化したと考えられます。
ベンガラと辰砂については古墳時代には既に魔除けとして広く用いられており、そうした使用が定着するにつれ、「丹」という言葉は顔料そのものだけでなく、その顔料がもたらす赤色をも指すようになりました。
すでにその時点で色材としての「丹」は神聖なものを扱う場面に限定されていたと思います。
そして、最も貴重な水銀朱が「丹の代表」となり、ベンガラが代表とならなかったことで「丹=辰砂」という認識が一般的になりました。これはある意味で「丹が土から離れた」状態だと言えます。
魏志倭人伝には「朱丹」という言葉が出てきます。この朱は丹を修飾している文字だと考えるのが自然です。
つまり「朱の丹=朱色の辰砂」という表現になるのだと思いますから、朱は赤系の色名なのです。
「朱」は古事記に登場しません。ただし、真朱も銀朱も続日本記(797年完成)に登場していますので、少なくとも平安時代が終わるまでには「辰砂を使った色」という意味の「朱」が一般的になっていたと考えて差し支えないと思います。 中国伝来の言葉なのですから、最初は日本も中国もほぼ同じ定義で、水銀朱の色を指していたのだと思います。
中国伝来の言葉なのですから、最初は日本も中国もほぼ同じ定義で、水銀朱の色を指していたのだと思います。
しかしながら、現在の朱色認識を調べるとこうなっていたりします。
これはWikipediaに出ている通りの記述です。
| 朱,朱紅/中国 | 朱色/日本 |
| #ef454a | #eb6101 |
これはかなり極端な例だと思いますが、それでも日本の朱色はオレンジに近いことが多いように思います。
そして、中国の朱は今でも真朱っぽいのです。
ここで丹塗りの推移が重要になります。
日本の神聖な塗装はいつしか「丹塗り」と呼ばれるようになります。まずは辰砂を使った色が「丹塗りの代表色」となりました。
水銀朱は丹塗り顔料の第一選択肢でしたが、非常に貴重であったため、古くから魔除けとして使われ色味も真朱に近いベンガラを、第二の選択肢として併用するようになりました。
その後、鉛丹が登場して室町時代に国内でも生産されるようになると、これが丹の有力な選択肢になっていきます。その影響で代用のベンガラは単体での使用が減り、丹塗りは次第に鉛丹の黄色みを帯びた色合いに寄って行ったと考えられます。
室町時代以降の選択肢はこうなりました。 A
A B
B C
C D
D
左から「鉛丹,銀朱,真朱1,真朱2、そしてベンガラ」です。
この流れは丹塗り顔料の着眼点を「どの程度黄色みがあるか」にしてしまったと思います。
おそらく、このような ともすればピンク系にも見える鮮やかな真朱については特別扱いだったのでしょう。
ともすればピンク系にも見える鮮やかな真朱については特別扱いだったのでしょう。
また、この頃までには「朱」という言葉が庶民にも広まっていたでしょうから、「丹塗り」は「朱塗り」とも呼ばれるようになっていたはずです。
丹であれば「丹を塗ること」ですが、朱の場合は「朱に塗ること」です。結局、丹塗りも朱塗りも「丹で朱に塗ること」になったと言えますね。
ベンガラをあまり使わないとなると「一般的な朱塗りのど真ん中の色」はBの位置になりますから、この頃は「 B
B 」の辺りを朱色と呼んでいたはずです。
」の辺りを朱色と呼んでいたはずです。
物質は同じですからその後の「バーミリオン=朱色」も妥当だと言えます。
西洋画は16世紀に伝来し、本格的な技術研究は江戸幕府八代将軍吉宗が禁書を緩和してからです。そうなると、最初からバーミリオンの製造方法を聞いた上で、和名をつけた可能性もありますね。
最初の和名は「銀朱」とされたのではないでしょうか。
さらに、地方によって差があったとは思いますが、鉛丹の使用頻度は圧倒的になっていきます。最終的な「ど真ん中」はAの位置だと思います。 A
A
かくして、このような色が今の日本の朱色認識の主流になりました。
もしも、鉛丹の製法が伝来せず、代用のベンガラがもっと活躍していれば・・
 C
C D
D
鮮やかな真朱を含めると元々はこんな感じの選択肢だったのですから、真朱そのものを朱色としていたはずです。そもそも「真の朱」と呼んでいたのですから当然ですよね。
まとめるとこうなります。
「丹=黄土・赤土」
→「丹=赤土・ベンガラ・辰砂」
→「丹=神聖な赤およびその顔料」
→「丹塗りの丹=朱塗りの朱=辰砂、ベンガラは代用」
→「丹塗りの丹=朱塗りの朱=辰砂と鉛丹」
→「丹塗りの丹=朱塗りの朱=ほぼ鉛丹」
・・・「朱色は鉛丹で塗った丹塗りの色」
現在では「丹」と「朱」は文脈によって異なる意味を持ちます。
丹色は決して丹の色ではないですし、水銀朱の朱と朱色は別物です。
そして丹色と朱色が同じとされることもあれば、区別される場合もあります。
また、朱色は鉛丹色に限定されず、当初の朱色である銀朱(バーミリオン)も朱色のままです。
幅としてはこんな感じでしょうか。
これらは全て「朱色」です。



「朱色」と言って真朱を指すのは、極めて限られた文脈の中だけです。
今では「朱色」と聞くと伏見稲荷のような色か、もっと黄色がかったオレンジ色を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。
でも、朱色は元来「真朱」なのですから、こういった色であるべきでした。


元に戻せないのですかね。
「鯛と言えば真鯛」「アジと言えばマアジ」ではなくなったようなものです。
真朱が「朱色」、バーミリオンの和名は「銀朱」、鉛丹の色については「鉛丹色」とするのが一番良かったように思います。
◆まとめ
2回に渡り、「丹」という顔料について探求しました。
朱色の推移にも見られるように、寺社の建造物に見られる鮮やかな赤は日本文化に深く根付いていますが、環境問題、健康被害といった課題に直面していることもわかりました。
伝統色が未来へと継承されるためには、こうした問題の早期解決が必須だと思います。 いつまでも原初の色彩が再現されることを願ってやみません。
次回はアカの完結編です。
ようやく「古事記の丹」の考察にたどり着きます。
お楽しみに。
| 当記事には筆者の推察が数多く含まれています。また、あくまでもInfigo onlineに興味を持っていただくことを目的としておりますので、参考文献についての記載はいたしません。ご了承ください。 |