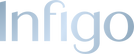日本人の青と緑⑧
⑥⑦が魚の回になってしまいましたが、「アカ」のお話に戻ります。
古事記のアカ (Part 1)で「赤」と「紅」について紹介しましたが、今回から「丹(に)」を見ていきます。
「丹」は認識の推移が非常に複雑なため、最初は色の特定どころではありません。
色材を調べることで多少は「丹」のことが見えてきましたので、ひとまずその結果を紹介することから始めます。
◆丹(に)とは
古来「丹」は土という意味です。
土は古代の赤色顔料の一つとされていますが、埴輪の「埴(はに)」がこの「丹」と同義です。
つまり、丹=埴=土ですので、赤土は最初「あかはに」と呼ばれていました。
近畿地方に赤土が多いためか、いつしか「丹」の読みに「あか」が加わり最終的には「顔料名および色名」となりました。
◆土そのもの? 土を修飾する言葉?
丹土(にど)
| #bf782b |
丹土は赤色顔料となる土のことで「につち」「たんど」とも読みます。
日本人は土の中から赤い鉱物を発見しては、それを祈りや占い、呪術、装飾として顔に塗っていました。このことから「顔料」という言葉が生まれたそうです。
丹土の「丹」が土を修飾している言葉だとすると、すでに「赤」という意味だったのかもしれません。そうなると丹土は単純に赤土を指す言葉になります。
赤土は土器や衣類の模様などにも使われてきましたが、酸化鉄の含有量によって赤みが変化します。
丹土が使われている塗装の代表に平等院鳳凰堂があります。
ほとんどの箇所について酸化鉄と黄土が混じった土で塗られていたことが判明し、平成の修復においてこの手法が再現されました。
鉄分の多い黄土を焼く、丹土ベンガラを使用しているそうです。
赤土を焼くと酸化鉄が増えてどんどん赤みが増すのですね。
弁柄(ベンガラ)
ここで人類史上最古の顔料であるベンガラを紹介しておきます。
酸化第二鉄を主成分とした赤土顔料のことで、戦国時代以降にインドのベンガル地方産が広まったことによってベンガラと呼ばれるようになったそうです。
粉末を入手して実際に塗ってみました。
確かに現在の平等院鳳凰堂の柱の色はベンガラ色ですね。
| ベンガラ | 塗ってみた |
 |
 |
世界的に有名なラスコー洞窟の壁画もベンガラの色です。
日本では縄文土器の塗装に始まり、古墳時代には魔除けとしてベンガラで壁を塗ったりしていたそうです。
酸化鉄には3種の結晶構造があり、以下のような色の違いがあります。
Fe2O3:赤 Fe2O3·H2O:黄 Fe3O4:黒
酸化第二鉄は赤と黄ですね。
四酸化三鉄の割合で印象も変わりそうです。
赤根沢の赤岩(青森県指定天然記念物)
このようにベンガラは天然で存在しています。
赤黄黒の混在が何となくわかりますね。
産地にはこうした岩がたくさん露出しているエリアがあり、赤の顔料として昔から重んじられてきました。
岩ではありますが、粉状になっていればベンガラ自体を「土」とみなすことにも違和感はありません。
このように最初から赤いベンガラもありますが、平等院の丹土ベンガラのように黄土を焼いて作ることもありますし、赤泥ベンガラ、パイプ状ベンガラ、など、天然材料を使って人工的に酸化第二鉄を生成する方法は数多くあります。
それだけ赤の需要があったということになります。
丹色(にいろ)
丹色という言葉/色があります。
文字通りだと「丹という色」あるいは「丹の色」です。
この丹は丹土の丹と同じであるか、「土」あるいは「赤土」ということになると思います。
| #f37053 | #ed6d46 | #e45e32 | #bd4d31 |
かなり幅がありますね。
定義としては「赤土のような黄みがかった渋い赤色」や「赤土の色で、赤みがかった灰黄色から赤褐色を表す色名」のように書かれています。
赤土は酸化鉄の割合で色味が違ってくるため幅があるのは当然ですが、これは本当に土の色なのでしょうか。
「神社仏閣の柱や梁、鳥居などに多く使用される特別な色」という記述もありました。これだと「丹塗りの色」と言っているのと同じです。
例えば「〇〇地方にある△△に使われた赤土の色」といった物質の定義があればわかりやすいのですが、この幅を見ると丹色は丹塗りありきで比較的新しい時代に再定義された言葉だと感じます。
つまり「丹色=丹塗りの色」となりますが、今の丹塗りの色は様々なので古事記の色の特定には使いづらい言葉です。
◆丹塗りの丹
「丹色=丹塗りの色」であれば、丹塗りの「丹」が何であるかが重要です。
今回の考察でこれを無視することはできません。

色々な言い方がありますが、丹塗りの辞書的定義はこのような感じになります。
- 丹または朱で塗ること。また、その塗ったもの
- 丹または朱を塗ること。また、そのもの。
- 丹朱(にあか)に塗ること。
百科事典的な説明ではこのような感じです。
一般に神社や寺院の朱塗りのことを指し、その鳥居・神殿や伽藍の朱塗りの華麗な表面仕上げをいう。権威を示すことと魔よけの意味を持ち、虫害や腐食から守る防腐剤の役割もある。
こうしてみると、土のことではないようですね。
ただ、丹塗りの説明に「朱塗り」と書かれても「朱塗りとは?」となってしまいますかね。
「丹朱=丹のあか」という意味ですから、基本的にこの「丹」は赤系色材で、「朱」は色名のように思えます。
ひとまず、土以外の丹の色材にどのようなものがあるのか見ていきましょう。
◎鉛丹
絵具の「丹」を調べてみると、まずは鉛を加熱して生成する鉛丹(四酸化三鉛:Pb3O4)というものが出てきます。鉛丹は現代の丹の代表です。文脈次第ですが「丹=鉛丹」だとされていることが非常に多いです。
| 鉛丹 | 塗ってみた |
 |
 |
絵具を入手して実際に塗ってみましたが、粉末も塗った色も赤というよりオレンジでした。
鉛丹色
| #ec6d51 | #d86554 | #cf4e40 | #d3503c |
鉛丹色とされていた色を4種取り上げましたが、ほとんど丹色と同じですし、実際に絵具で塗った色とは全く印象が違います。
粒子の大きさによって多少印象が変わるとは思いますが、差が大きいですね。
どういうことなのでしょう?
鉛丹は昔からさかんに寺社の鳥居などの塗装で使われてきました。
丹塗りで最も多く使用されてきた顔料で、酸素を遮断する性質があるので建築鉄骨の錆止め塗料にも使われています。
正倉院にも保存されているそうですが、それは大陸から伝来したものです。
奈良時代あたりから使用が始まり、生成方法は室町時代に伝来したそうです。
日本には各地に鉛鉱床があったため、その後たくさん製造されるようになりました。
最初は1395年に鉛屋市兵衛という人が鉛丹の製造方法を明人から学んで生産を開始したそうなのですが、驚いたことにこの会社(NIケミテック株式会社)は続いていて、未だに鉛丹を寺社に提供しています。
◎水銀朱(辰砂)
辰砂(しんしゃ)という鉱物から取り出される水銀朱(硫化第二水銀:HgS)も赤の顔料として縄文時代から使われている「丹」です。
国内には辰砂産地が200ヵ所以上もありました。
西日本では中央構造線に沿って集中しています。
そもそも「丹」は中国伝来の言葉で、中国では「丹=水銀朱」です。
辰砂という名称も辰州という中国にあった地名から来ています。
辰砂

上質の天然辰砂から作られた水銀朱の色は真朱(しんしゅ)または本朱(ほんしゅ)と呼ばれ、HgSを人工的に生成して作られた色は銀朱(ぎんしゅ)と呼ばれていました。
平安時代までには銀朱の製法が確立されていたそうです。
| 真朱 | |
| #ef454a | #ab3b3a |
| 銀朱 | ||
| #f26649 | #e24215 | #c73e3a |
これらも幅が大きい感じがしますが、銀朱の方が黄色みが強く、真朱が落ち着いた色という認識であることは想像できます。
「真の朱」と呼んでいたのですから、真朱が元祖朱色ということになります。
また、「丹」と違い「朱」は色名から始まったのだと思います。
顔料自体を真朱・銀朱と呼ぶようになったことで「朱=水銀朱」という認識が後から広まったのでしょう。
水銀朱についても絵具を3種類入手して塗ってみました。
| Type | 絵具 | 塗ってみた |
| 真朱 |
 真朱 |
 真朱 |
| 銀朱 |
 鎌倉朱 |
 鎌倉朱 |
| 銀朱 |
 赤口本朱 |
 赤口本朱 |
真朱のほかに「鎌倉朱」「赤口本朱」という銀朱も入手しました。
現在の製造技術が高いためか、人工でもかなり真朱に近い色ですね。
何らかの方法で真朱に寄せているのでしょう。
本朱という言葉は複雑で「水銀由来でない朱色に対しての本物」という意味合いでも使われているようです。
画像の赤口本朱のように、人工であっても「本朱」と呼ぶことがあるのです。
確かに似ているのですが、実際は全然違います。
画像にして伝えることは難しかったのですが、真朱にだけ極めて微細な光があり、印象が全然違うのです。
「ほんのりキラキラしたマット仕上げ」といった感じでしょうか。
キラキラしてはいますが非常に上品で、神聖な物に塗られるようになった意味がよくわかります。
天然辰砂ではHgS以外の物質の影響が非常に大きいのですね。
人工HgSの色はバーミリオンとも呼ばれ、油絵をやる方々には馴染みのある朱色です。
硫黄成分の含有量が増すと黄色みが出てくるようですので、より純度の高い銀朱ということになります。
| バーミリオン | |
| #ea553a | #e34234 |
日本の最初の朱色は真朱であったはずなのですが、西洋画の世界で朱色と言えばこの色になります。一般的にも朱色はこうした色を指すと思います。
でも、どういう経緯でバーミリオンの日本語名が「朱色」となったのでしょう。
新たな疑問です。
辰砂の歴史は多彩で、水銀が不老長寿の薬とされていた時代もあり、それで寿命を縮めた人が数多くいます。秦の始皇帝や漢・唐の歴代皇帝の多くが水銀中毒になっています。
また、ヨーロッパでは16世紀あたりから数百年の間、水銀が梅毒などの治療薬として広まります。
31歳という若さでこの世を去ったシューベルトは、水銀を使用して寿命を縮めた可能性があります。だとすれば、そんな治療法さえなければ交響曲7番が未完成で終わることはなかったということになります。
日本では全国に「丹生」の名が付く地名や神社があり、それらは全て辰砂の採掘場所です。
水銀鉱山の中には空海が開山したと伝わる場所も多く存在し、高野山で山岳修業したことは辰砂に大きく関係しているようです。
高野山の麓には丹生(にう)氏という一族が住んでいて、水銀の生産で繁栄していました。
関ヶ原の戦いの後に真田信繁が配流されたのも高野山で、後に高野山の表参道口にあたる九度山に移住しますが、その周辺にも「丹生」の名が付く神社が数多くあります。
信繁は大坂の陣で赤備えを率いて現れますが、辰砂の産地が近かったのですね。
真田幸村公甲冑(レプリカ)
(提供:上田市マルチメディア情報センター)
画像はレプリカですが、この色はどちらかと言えば銀朱のような気がします。
こうした丹生の地では銀朱の生成も行っていたことでしょう。
◆まとめ
ひとまず今回はここまでです。
最初の朱色が水銀朱の色であり、基本的に「丹=水銀朱」であったことはわかりましたが、丹塗り誕生時の丹が水銀朱であったかはわかりません。
一番最初は丹土であった可能性も十分にあると思いますが、その証拠が出てくることは考えづらく、このことは永遠に確定しないでしょう。
ただ、縄文時代から使われていることを踏まえても、丹塗りの丹は当初から水銀朱であったと考えるのが妥当だと思います。
次回は丹塗りの実例を見ていきます。
お楽しみに。