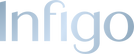日本人の青と緑⑫
前回は冠位十二階を考察しました。
今回は冠位制度のその後を見ていきます。
◆七色十三階冠
日本書紀によると、七色十三階冠(ななしきじゅうさんかいかん)という、冠位十二階のバージョンアップ版のような制度が647年に制定され、648年に施行されています。
冠位十二階とは45年ほどの違いなのですが、七色十三階冠が制定される2年前に乙巳の変がありました。つまり、この冠位制度の改定は「大化の改新」そのものです。
ここでようやく具体的な色名が出てきますが、当然冠位十二階の色予想にも影響したはずですね。紫、真緋(あけ)、紺、黒、緑が出てきます。
七色十三階冠は冠の素材や縁取りと装飾品および服の色の組み合わせによって冠位を表現する仕組みになっています。冠の素材と服の色を整理してみました。
| 冠位 | 冠の素材/色 | 服の色 | |
| 1 | 大織 | 織/深紫? | 深紫 |
| 2 | 小織 | ||
| 3 | 大繡 | 繡/深紫? | |
| 4 | 小繍 | ||
| 5 | 大紫 | 紫 | 浅紫 |
| 6 | 小紫 | ||
| 7 | 大錦 | 大伯仙錦/赤? | 真緋 |
| 8 | 小錦 | 小伯仙錦/赤? | |
| 9 | 大青 | 青絹 | 紺 |
| 10 | 小青 | ||
| 11 | 大黒 | 黒絹 | 緑 |
| 12 | 小黒 | ||
| 13 | 建武 | 記述なし |
織・繡・紫・錦・青・黒はそれぞれ「しき(おりもの)・しゅう(ぬいもの)・し(むらさき)・きん(にしき)・しょう(あお)・こく(くろ)」と読みます。
どうも全体的に五行説からは離れた感じがします。
紫について
1,2位の大織(だいしき)・小識(しょうしき)と3,4位の大繡(だいしゅう)・小繡(しょうしゅう)については素材の記述しかないのですが、服が深紫ですから冠の色も紫系でしょう。5,6位の冠が紫という記述があるので1~4位は深紫だと思います。あるいは上に行くにしたがって濃い紫にしていたかもしれません。
このことは「冠位十二階の最上位が紫」の説を十分に補強しています。むしろ、一番のエビデンスなのかもしれません。
冠位十二階では蘇我蝦夷が入鹿に勝手に紫冠(むらさきのこうぶり)を授けたという話もありますし、漢の武帝が好んで以降、中国でも紫は高貴な色とされていますので「一番上は紫」で問題ないでしょう。
錦と真緋について
「錦」は金銀などの色糸を用いて、模様を織り出した織物のことです。織り方に関係なく、二色以上の色糸を使って文様を出した華やかな織物を錦と呼んでいたようです。錦冠には伯仙(はくせん)という模様があったのだと思いますが、それがどういったものなのかはよくわかりません。
色の記載もありませんが、服と同じ赤系と考えるのが自然です。正倉院宝物の錦にこういう物がありました。

(出典: 正倉院宝物)
模様はわかりませんが、このような色味だった可能性は高いと思います。
ただし、茶系や黄・金といった色の可能性もゼロではないです。古くは全部「アカ」でしたから、黄も茶も服の色と同系色と考えられていたかもしれません。中国では紫と並び黄色も高貴な色でしたから、紫の一つ下を黄色にしたというストーリーでも面白いです。

例えば上の画像のような錦は中国では「黄」だと思います。
あるいは隋では柘黄(しゃおう)という色が朝廷に出仕する際の衣類に使われ、冠もこの色だったそうなので、それに習った可能性もあると思います。
| 柘黄 | 緋色 |
| #c67915 | #c73c2e |
服に使われた真緋(あけ)は伝統の赤です。平安時代から「緋色(ひいろ)」と呼ばれるようになります。茜染めの中で、一番鮮やかな黄みのある赤が緋色です。
二色とも黄色みがあって相性が良さそうです。緋色の服に柘黄の冠は非常に良い組み合わせに思えますが、いかがでしょう? 両方を緋色にするよりいいですよね。
青と緑について
青系に目を向けましょう。9~12位です。
青絹、紺、緑と出てきます。
| 縹色 | 紺 | 緑 |
まず青絹と表現された素材は藍染めしたものである可能性が高いです。この色は後に縹色(はなだいろ)と呼ばれるようになりますが、純粋に藍だけで染めた色であり、今の青の原点です。
また、紺は「深き縹(ふかきはなだ)」とも呼ばれる藍染の最も濃い色です。藍染めの成分には赤系の染料が含まれていて、濃染めするとそれが現れて紺になるそうです。
不思議なことに元々の「藍色」というのは藍だけで染めた色ではなく、純粋な藍染に黄蘗(きはだ)という黄色を混ぜた色のことだったそうです。キハダはミカン科の落葉高木で、樹皮内部に黄色成分があります。
| 紺 | 黄蘗 | 藍色 |
当時、この藍色と緑色の染料は同時に使われるようになったかもしれません。あくまでも想像ですが、その藍色は緑を作る過程でたまたま生まれた副産物だと思います。
緑は単一の染料で出せる色ではありませんので、必ず青系と黄色を混ぜる形になります。
| 縹色 | 黄蘗 | 緑色 |
緑については平安時代の記述までヒントがないようですが、早い時点でこのような染料の開発ができていたと思われます。レシピが完成していなければ「緑の服を着用」というルールにするはずがありません。
そして、縹が紺に近くなると黄色の割合次第で当時の藍色になりますから、この色は緑の色味を調整する過程で生まれるはずなのです。
ただ、今は藍染の色彩全体を藍色と呼ぶようになっていて、むしろ黄色みが少ない方が藍色と認識されやすいようです。
何はともあれ、七色十三階冠では青と緑が完全に区別されていますね。そうなると冠位十二階の青がブルーであることを疑わないのは自然なことかもしれませんが、七色十三階冠は五行説から離れた日本独自の色使いが目立ちますので「冠位十二階において緑にしていた冠を七色十三階冠になって青に変更した」ということも十分あり得ます。やはり、冠位十二階の有力説の「青」は緑色にすべきだと思います。
◆冠十九階
七色十三階冠は648年の4月に施行されましたが、翌649年に冠十九階というさらなる改正版に変わります。こちらも大化の改新コンテンツの一つです。
日本書紀に冠十九階の色名は出てきません。代わりに有職図譜(ゆうそくずふ)という書物にこのときの冠一覧が載っていました。冠の絵と服の色名が載っています。この書物の制作時期は不明とされていますが、内容から室町時代か江戸時代の書物だと思われます。
冠十九階は「錦青黒」の3つの冠位がさらに分割して6種類増えただけですので、七色十三階冠の色について考える際の手がかりにもなります。
信憑性も未知数ですが、図がカラフルで楽しいので抜粋して紹介しておきます。
| 大織 | 小織 | 小繡 | 大華上 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 大山上 | 大乙下 | 小乙下 | 立身 |
大山上という冠位は大青の発展形なのですが、冠の青が緑に変わっています。服も深緑に変わっています。結局、七色十三階冠の青絹の冠と紺の服は全部緑系になっていました。

しかも、これらの緑冠は縹の冠より上に来ています。緑は藍染に黄色を足すからということですかね。緑の方が手間が掛かる以上、縹より上位に来るのが自然かもしれません。ブレンド色を単独色材の色よりも重んじるのは非常に日本的です。
「錦」という名称は無くなって「華(花)」になっています。豪華すぎてバランスが悪かったのでしょうか。他の冠にも錦を使うためだったかもしれません。
なお、冠十九階の記述に関しては「青」という言葉が使われていません。「青」は曖昧ですから、確かに「縹」と「緑」を使った方が安心ですね。
藤原鎌足
冠十九階の「大織」に関しては2024年に大きな発表がありました。
1934年に大阪府高槻市で京都大学地震観測所の掘削工事の際に古墳が発見されたのですが、このとき多くの装飾品と人骨が見つかりました。阿武山古墳と名付けられています。皇室の古墳である可能性の指摘を受け、発見から111日後に埋め戻されたそうなのですが、1982年に被葬者のX線写真の存在が明らかになり、京大でその画像解析が行われました。
まずは発見当初の様子と画像解析結果によって以下のことがわかっていました。
●脊椎を骨折し、下半身不随で数カ月間過ごした後に亡くなった。
●左肘がスポーツ肘で、ヒ素を服用していた。→「弓矢に長じていた」
●金糸の刺繍が入った冠を着用し、埋葬されていた。
そして近年さらなる解析が行われ、この冠の生地が綴織(つづれおり)という特殊な織りによる物だとわかり、この被葬者は669年に亡くなった藤原鎌足である可能性が非常に高いと2024年に報じられました。
◆織生地の冠は大織と小織のみ
◆中臣鎌足は死の直前に天智天皇から藤原という姓と大織冠(たいしょっかん)を授けられた
◆織冠を授けられた記録は2件しか存在せず、もう一人は百済人である
◆藤原鎌足は亡くなった年に狩りで馬上から転落し、背中を強打していた
◆弓の達人でもあって古墳に埋葬されるほどの人物
これだけ揃えばもう間違いありません。
日本書紀の精度も驚きですね。この件に関しては虚偽も誇張も無さそうです。
下の画像は最新の発表の際に公開された復元大織冠です。
(画像: 毎日新聞)
金糸部分の模様については定かではないようですが、花の刺繍や縁の模様は精密に再現できているのだそうです。歴史上2回だけなのですから、先の大織の図はこれを描く必要があったということになります。
想像で描いたはずですが、随分雰囲気は違いますね。生地にカラフルな模様があった訳ではなさそうです。
ただ、花びらなどを散りばめていた可能性はありますね。日本書紀には全く出ていませんが、花飾りは自由だったのかもしれません。
◆まとめ
「青」は七色十三階冠の「大青・小青」という2つの冠位名とその材料である「青絹」にしか出てきませんでしたが、冠十九階の図を見る限りこれらは縹色だと思われます。
緑が完全に区別され、色名としてきちんと使われていた可能性も高いと感じました。
ただし、「青絹・緑絹」というようには出てきていません。同様に「緑の服に青い服」といった対比表現もありません。
間違いが許されない環境ということもあるでしょうが、結局「青は色名ではなく色ジャンル名」だったのではないでしょうか。「青と緑」というような考え方はまだ無かったのだと思います。
| 当記事には筆者の推察が数多く含まれています。また、あくまでもInfigo onlineに興味を持っていただくことを目的としておりますので、参考文献についての記載はいたしません。ご了承ください。 |