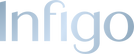平安時代の緑
ここでは平安時代の緑がどういった領域で使われていたかを可視化してみました。
これまでの考察を踏まえて緑の領域を下のような「blue~green~yellowgreen」のチャート例で想像しています。
| 縹 | 縹 | 縹 | 縹 | 縹 | 浅縹 | 浅縹 | 浅縹 |
| 縹 | 縹 | 縹 | 縹 | 縹 | 浅縹 | 浅縹 | 浅縹 |
|
縹 |
縹 |
縹 |
縹 |
縹 |
浅縹 |
浅縹 |
浅縹 |
| 浅葱 |
浅葱 |
浅葱 |
薄浅葱 浅縹 |
薄浅葱 浅縹 |
薄浅葱 浅縹 |
||
| 浅葱 |
浅葱 |
浅葱 |
薄浅葱 |
薄浅葱 |
薄浅葱 |
||
| 浅葱 |
浅葱 緑 |
浅葱 緑 |
薄浅葱 浅緑 |
薄浅葱 浅緑 |
薄浅葱 浅緑 |
||
|
|
|
緑 | 緑 |
浅緑 |
浅緑 | 浅緑 | |
|
|
|
緑 |
緑 |
浅緑 | 浅緑 | 浅緑 | |
| 緑 | 緑 | 浅緑 | A 浅緑 |
B 浅緑 |
|||
| 緑 | 緑 | 浅緑 |
C 浅緑 |
D 浅緑 |
|||
| 緑 | 緑 | 浅緑 | 浅緑 | 浅緑 | |||
| 緑 | 緑 | 緑 | 萌黄 | 萌黄 | |||
| 緑 | 緑 | 緑 | 萌黄 | 萌黄 | |||
| 緑 | 緑 | 緑 | 萌黄 | 萌黄 | |||
| X | 緑 | 緑 | 緑 | 萌黄 | 萌黄 |
こんな感じでしょうか。まず、萌黄色の箇所を除くと全て「青」という色グループではあったはずです。そして、右の方に緑系が寄っていたと考えます。
この時代、「青」と「緑」で色相をはっきり区別するということはなく、「青」と「緑」は混用されていましたが、ある程度の法則があったはずで、「緑」は「明度が高い青緑から緑」および「新緑のような黄緑に近い色」に使われやすかったと思います。
私たちが「典型的な緑」と感じるXは「緑」と呼んでいなかった可能性が高いです。こういう濃いgreenや暗めのgreenは「青」としか呼ばれなかったのではないでしょうか。何も書かなかった箇所の呼び方は全て「色名=青」だと思います。もちろん、もっと暗く灰がかっていたり、くすんでいたりしても「青」です。
現在だと青緑に思える辺りに浅葱色があります。
ただし、以前の記事でも紹介しましたが、「薄い瑠璃色」とされています。少しだけgreenが入った感じのライトな藍染めです。greenに近い側はそのまま「緑」とも呼ぶこともあったでしょうし、淡い「薄浅葱」はほぼ水色なので「浅縹」でもあります。
この辺りは浅縹、浅緑、浅葱色と様々な呼び方をしていたでしょう。
ただ、本来の浅緑はもう少し黄緑に近いABCDの辺りがメインだったと思います。